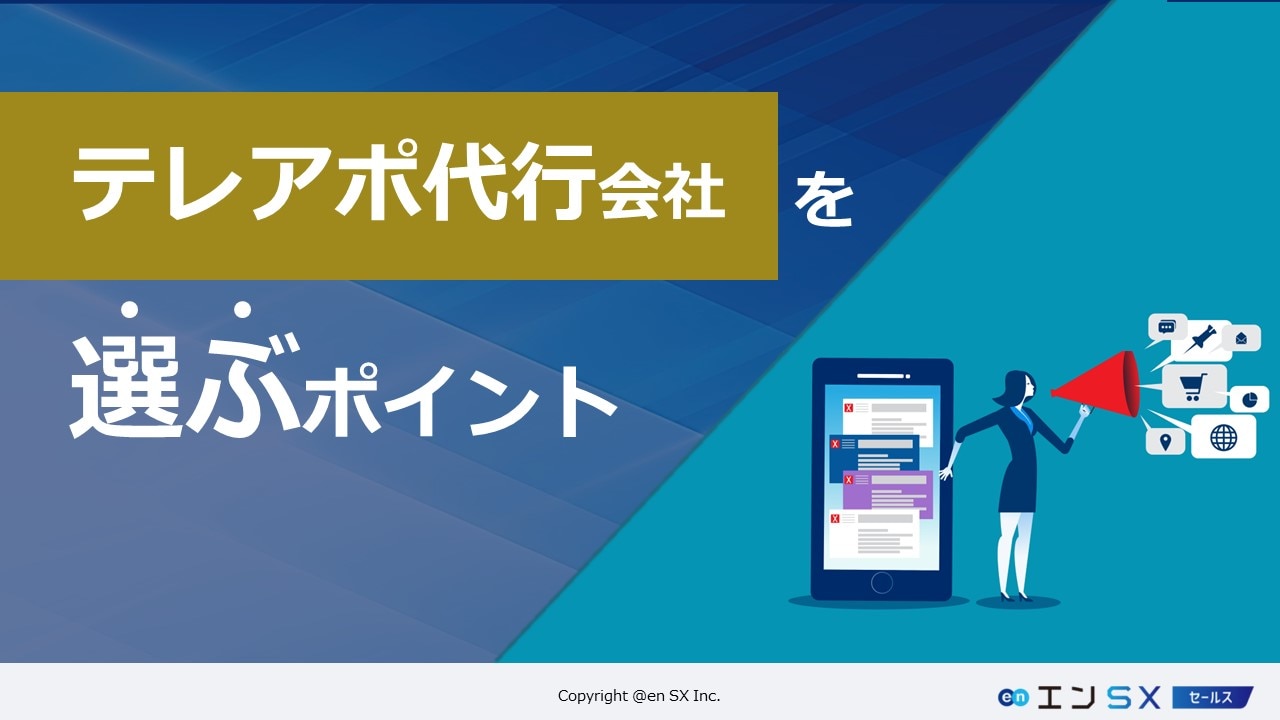SIer向け新規開拓の極意|インサイドセールスで属人化脱却
SIer企業にとって新規開拓は売上成長の鍵ですが、従来のテレアポや飛び込み営業は効率の限界に直面しています。多くの企業が属人化に悩み、再現性のある営業仕組み作りを模索している状況です。
本記事では、SIer特有の営業課題に寄り添い、特にインサイドセールスを活用した新規開拓の成功ポイントを徹底解説。導入のメリットや具体的なKPI設定、内製か外注かの判断基準、さらには実際の成功事例までを網羅し、属人化脱却と営業効率化を実現するための実践的なノウハウをお届けします。
目次[非表示]
SIerの新規開拓が抱える営業課題とは?
従来営業手法の限界と属人化の問題
飛び込み・テレアポの効果減少の背景
かつてSIer業界では、飛び込み営業やテレアポといった「足で稼ぐ」営業が新規開拓の主力でした。しかし近年、企業側のセキュリティ意識や個人情報保護が強化され、飛び込みの門前払い、テレアポ拒否が急増。加えて、コロナ禍以降はリモートワークが定着し、電話や訪問自体が届かないケースも増えました。こうした背景から、物理的な接触ベースの営業活動は、効率・効果の両面で限界を迎えています。
個人依存の営業スタイルのリスク
属人的な営業体制は、企業の持続的成長を阻害する大きな要因です。スキルや人脈に依存する体制では、特定の担当者が抜けた途端、売上が激減するリスクがあります。また、営業ノウハウの体系化が不十分なため、育成にも時間がかかり、成果の再現性が低くなります。再現性のある営業体制構築には、個人技から組織的なプロセス設計へのシフトが必要です。
新規リードの質と量のバランス問題
多くのSIerでは、リード数を確保することに重点が置かれる一方で、質の担保が疎かになりがちです。たとえば、メールや展示会で得た名刺がリードとして扱われるケースもありますが、商談化率は極めて低いのが実情です。逆に質にこだわりすぎると件数が不足し、営業稼働が空回りすることも。効率的に商談へつながる「量と質の最適バランス」が、営業設計上の重要な論点となります。
営業成果の属人化と平均変換率のギャップ
売上拡大の壁〜なぜ新規開拓が重要か
既存顧客からの成長限界
既存顧客への深耕営業は、信頼関係の構築や安定収益に寄与する一方で、売上成長率には限界があります。特に、システムの大規模更改サイクルが5~10年単位であるSIerでは、既存案件の更新頻度が低く、新規導入を伴わないと年間5%以下の成長にとどまるケースもあります。成長を維持するためには、新規顧客の獲得が不可欠です。
競合他社との差別化難化
近年、技術的な差別化が難しくなり、SIer各社が似たようなサービス・提案をするようになっています。そのため、価格競争に巻き込まれるリスクが増大。差別化のためには、業界理解や業務改善提案といった「付加価値営業」が求められますが、新規開拓を通じて多様な業種にアプローチする中でこそ、これらの経験や視点は養われていきます。
市場環境変化とニーズの多様化
クラウド化・DX・サブスクリプションビジネスなど、IT業界は急速に変化しています。クライアントのニーズも「インフラ整備」から「事業支援」へと進化しており、SIerもそれに応じた変革が求められます。新規開拓は、こうした変化を肌で感じ取る場でもあり、次世代型ソリューション提案の布石として重要な機会となります。
既存顧客 vs 新規開拓の年間売上成長率比較
インサイドセールスとは?SIerに必要な理由
インサイドセールスの基本概要
インサイドセールスの定義と役割
インサイドセールスとは、電話やメール、オンラインツールを用いて非対面で顧客とコミュニケーションを取り、リードの発掘・育成・商談化を促進する営業手法です。特にIT・SIer業界では、顧客の技術的な理解やニーズが複雑であり、初期段階で効率よく情報収集と適切な案件選別を行うことが求められます。インサイドセールスは、営業の“前段階”として、フィールドセールス(対面営業)への商談引き渡しを担う役割を果たし、営業プロセス全体の効率化と再現性向上を支えます。
従来営業との違い
従来の営業スタイルは主に飛び込みやテレアポ、訪問営業に依存しており、営業担当者の経験や人脈に左右される属人的な要素が強いのが特徴でした。一方、インサイドセールスはCRMツールやMA(マーケティングオートメーション)を活用し、データに基づいたリード管理と顧客接点の最適化を行います。これにより、成果の見える化や営業活動の標準化が可能となり、組織的な営業力強化を実現します。
営業プロセスにおける位置付け
営業プロセスは「リード獲得 → リードナーチャリング → 商談 → クロージング」という流れですが、インサイドセールスは主にリード獲得後から商談前までの「リードナーチャリング(育成)」フェーズを担当します。具体的には、興味関心がある潜在顧客に対して情報提供や課題ヒアリングを繰り返し、商談に進める「温度感の高い」リードへと育て上げます。これにより、フィールドセールスは受注確度の高い案件に集中でき、効率的な受注活動が可能となります。
SIer営業におけるインサイドセールスのメリット
効率的なリード育成と管理
SIerの新規開拓は、技術的な説明や業界特有の課題理解が不可欠で、潜在顧客の検討期間も長い傾向があります。インサイドセールスは、段階的に顧客の課題やニーズを把握し、適切なタイミングで情報提供を行うことで、リードの育成効率を飛躍的に向上させます。これにより、無駄な商談設定を減らし、営業活動の効果最大化を実現します。
属人化しにくい仕組み化の可能性
CRMやMAを活用した営業活動のトラッキングにより、個人の経験や勘に頼らない営業フローを構築できます。結果として、ノウハウの共有・蓄積が促進され、新人教育の効率化や営業メンバー間の成果の均質化が期待されます。特に技術者が営業に兼務しているSIerにおいては、営業活動の仕組み化が強い味方となります。
コスト削減とROIの向上
フィールドセールスが直接訪問するコストや時間を削減できるため、営業コスト全体の最適化につながります。インサイドセールスはリモートで多くのリードと接点を持てるため、ROI(投資対効果)が高い手法です。米国の調査によれば、インサイドセールスを導入した企業は従来営業に比べ、営業コストを最大30%削減しながら売上を10〜20%向上させた事例もあります。
インサイドセールス導入前後の営業効果比較(米国SIer事例)
アウトバウンド・インバウンドの使い分け
アウトバウンド型インサイドセールスの特徴
アウトバウンド型は、企業側から積極的に見込み客へアプローチをかける手法です。SIerでは新規顧客開拓に活用され、ターゲット企業リストを基に電話やメール、SNSを活用してリード獲得を目指します。メリットは能動的に市場に接触できることですが、リードの反応率が低い点が課題です。
インバウンド型インサイドセールスの特徴
インバウンド型は、ウェブサイトやセミナー、ホワイトペーパー等で顧客の自発的な問い合わせを促し、その反応をインサイドセールスがフォローする形です。受動的なアプローチながら、反応者の購買意欲は高い傾向にあります。SIerでは、マーケティング施策と連携することで質の高いリード獲得に繋がります。
SIerに適した活用シーン
SIerの営業活動においては、アウトバウンドで新規顧客候補を幅広く掘り起こしつつ、インバウンドで問い合わせや資料請求などから質の高いリードを受け皿にする「ハイブリッド運用」が理想的です。特に、提案内容が専門的で購買意思決定に時間がかかるSIerでは、長期的なリード育成が不可欠なため、両者の役割を明確に分けて運用することで営業効率が飛躍的に高まります。
インサイドセールスの特徴比較
SIerの新規開拓の具体的施策
属人化を防ぐKPI設計と運用ポイント
リード獲得数の設定方法
SIerの営業活動で重要なのは、属人化を防ぐために明確なKPIを設計し、数字で成果を可視化することです。まずリード獲得数は、過去の営業実績や市場規模、ターゲット層の反応率を元に設定します。一般的に、SIerの新規開拓営業では、リード獲得数と商談化率の掛け合わせが最終受注件数の鍵となるため、過去データを分析し「最低限必要なリード数」を算出することが重要です。例えば、月間10件の受注目標に対し、商談化率が10%なら最低100件のリード獲得を目指します。
アポイント獲得率の改善施策
アポイント獲得率はリードの質と営業トーク、タイミングが大きく影響します。効果的な施策としては、顧客の課題に寄り添った提案内容のブラッシュアップや、トークスクリプトの標準化・改善が挙げられます。さらに、リードの属性・行動データを活用して、より関心の高いターゲットに優先的にアプローチすることが有効です。営業チーム内で成功例を共有し、PDCAサイクルを回すこともアポイント率向上に欠かせません。
商談化率のモニタリング方法
商談化率は、リードから実際の商談に至る確率であり、営業プロセス全体の質を示す指標です。定期的にCRMなどのツールでデータを収集し、リードの属性別や担当者別の商談化率を比較分析します。異常値があれば原因を探り、営業手法やリード選定基準の改善につなげることが肝要です。また、営業プロセスの各段階での滞留時間を可視化し、ボトルネックを特定することも有効です。
定期的なデータ分析の重要性
データ分析は、営業活動の「見える化」と「再現性向上」の要です。月次や四半期ごとにKPIを振り返り、数字の変化に対して柔軟に施策を見直します。特に新規開拓では市場環境や顧客ニーズが変動しやすいため、データを軸にした迅速な意思決定が競争力強化につながります。さらに、営業・マーケティング両部門で情報を共有し、連携した分析を行うことが成功の鍵です。
SIer新規開拓における主要KPI例
チーム内での情報共有と連携の工夫
CRMツールの活用
SIerの営業チームが属人化を防ぎ、効率よく新規開拓を進めるためには、CRM(顧客関係管理)ツールの活用が不可欠です。CRMは顧客情報、リードの状況、商談履歴などを一元管理できるため、チーム内での情報共有がスムーズになります。例えば、リードがどの段階にあるか、どんな課題を持っているかをリアルタイムで把握できることで、営業担当者間の連携が強化され、重複アプローチや見落としを防止できます。さらに、営業活動のデータを蓄積し分析することで、改善点の抽出や戦略のブラッシュアップも容易になります。
営業とマーケティングの連携強化
新規開拓においては営業だけでなく、マーケティング部門との連携も非常に重要です。マーケティングはウェビナーやホワイトペーパー、SEO対策などでリードを獲得し、営業はそのリードを引き継いで育成・商談化を目指します。両者が連携し、リードの質を高めるための基準設定や、情報のタイムリーな共有を行うことが必要です。例えば、マーケティングからのリードの反応率を営業側でフィードバックし、キャンペーン内容の改善に活かすといったサイクルを回すことが効果的です。
フィードバックループの設計
営業現場で得られた顧客の声や市場の変化は、迅速にチーム内で共有し、営業手法やマーケティング施策に反映させる必要があります。定期的なミーティングやオンラインツールでの情報共有を通じて、フィードバックループを設計することで、営業プロセスの最適化が図れます。特にSIerのように技術的な要素が強い場合、技術部門との連携も含めた多角的なフィードバックが成功の鍵となります。
SIer新規開拓における情報共有・連携のポイント
▼エンSXでのSIer支援事例はこちら
https://sales.en-sx.com/case/primeware
内製化か外注か?SIerの営業体制の選び方
インサイドセールスを内製するメリット・デメリット
内製化の長所(ノウハウ蓄積・柔軟対応)
SIerがインサイドセールスを内製化する最大のメリットは、自社の営業ノウハウや顧客特性を深く理解した上で、柔軟に営業戦略を立案・実行できる点にあります。内製化により得られるナレッジは長期的な資産となり、技術的な製品知識や業界特有の課題に即した提案力の強化に直結します。また、営業チームと開発部門や技術部門との連携も円滑になり、顧客ニーズに応じた迅速な対応が可能です。
内製化の課題(初期投資・運用負荷)
一方で、内製化には人材採用・育成、システム導入、管理体制構築といった初期投資や運用負荷がかかります。特に、インサイドセールスの専門知識や経験を持つ人材の確保は難易度が高く、育成期間も必要です。また、営業チームの運営にあたっては、効果的なKPI設計やデータ分析体制の整備が求められ、これらを社内で継続的に行う体制づくりが課題となります。
インサイドセールス内製化と外注の比較
外注(アウトソース)活用のポイント
外注のメリット(即戦力・コスト最適化)
アウトソースによるインサイドセールス活用は、即戦力としての専門家の投入が可能であり、初期投資や人材育成コストを抑制できるメリットがあります。特に営業リソースが限られているスタートアップや中小SIerにとっては、柔軟な契約形態で必要な期間だけ外部に依頼することで、コスト効率の高い営業活動が可能です。
外注のリスク(情報漏洩・品質管理)
しかし、外注に伴うリスクもあります。顧客情報の漏洩リスクや、外部スタッフの営業品質が自社基準に達しない場合があるため、情報管理の厳格化や品質監査体制の整備が不可欠です。また、外注先とのコミュニケーション不足により、現場の細かなニーズや市場変化を反映しにくくなる可能性もあります。
委託先選定のポイント
外注先を選定する際は、SIerの業界理解度や営業実績、対応可能なサービス範囲、セキュリティ管理体制を重視しましょう。さらに、契約前にトライアル期間を設けることで、実際の営業パフォーマンスや連携のしやすさを見極めることが推奨されます。
外注先選びで失敗しないために|選定時のポイントを押さえた資料はこちら
テレアポやインサイドセールスの外注を検討する際、「どの会社に依頼すべきか」「何を基準に選べばよいか」は非常に悩ましいポイントです。失敗しない選定のためには、業界特性や営業体制に合った外注先を見極める視点が欠かせません。
以下の資料では、営業代行・テレアポ代行会社を選ぶ際に押さえるべき重要なポイントを網羅的に整理しています。比較検討のチェックリストとしても活用可能です。
👉 資料を無料でダウンロードする(テレアポ代行会社を選ぶポイント)
ケース別に考える最適解の見つけ方
事業規模・リソース別の判断基準
内製化か外注かの選択は、事業規模や保有リソースに大きく依存します。大規模SIerや営業経験豊富なチームがある場合は内製化が適し、一方でリソース不足や急成長フェーズの企業は外注を活用することで効率的に営業力を強化できます。
成長ステージに応じた選択肢
企業の成長ステージも選択の重要な指標です。スタートアップ期は外注でスピード重視の営業展開を行い、事業が安定・拡大するにつれて内製化を進める「ハイブリッド」型の活用も効果的です。
パイロット導入のすすめ
内製化や外注のどちらを検討する場合も、まずはパイロットプロジェクトとして限定的に導入し、効果測定と課題抽出を行うことが推奨されます。この段階で得た知見を基に、最適な体制を構築することで、リスクを最小限に抑えられます。
まとめ:属人化を脱する営業戦略
SIer業界では、従来の飛び込み営業やテレアポの限界、属人的な営業体制、リードの質と量のバランスなど、新規開拓における課題が山積しています。中でも「属人化から脱却できず、再現性のある営業体制が築けない」という悩みは、多くの現場で共通しています。
こうした課題に対しては、インサイドセールスを軸とした“構造設計”による営業プロセスの最適化が有効です。属人的なスキルに頼らず、成果が出る仕組みを設計することが、持続的な成長の鍵となります。
“成果が出る営業体制”を仕組みでつくる
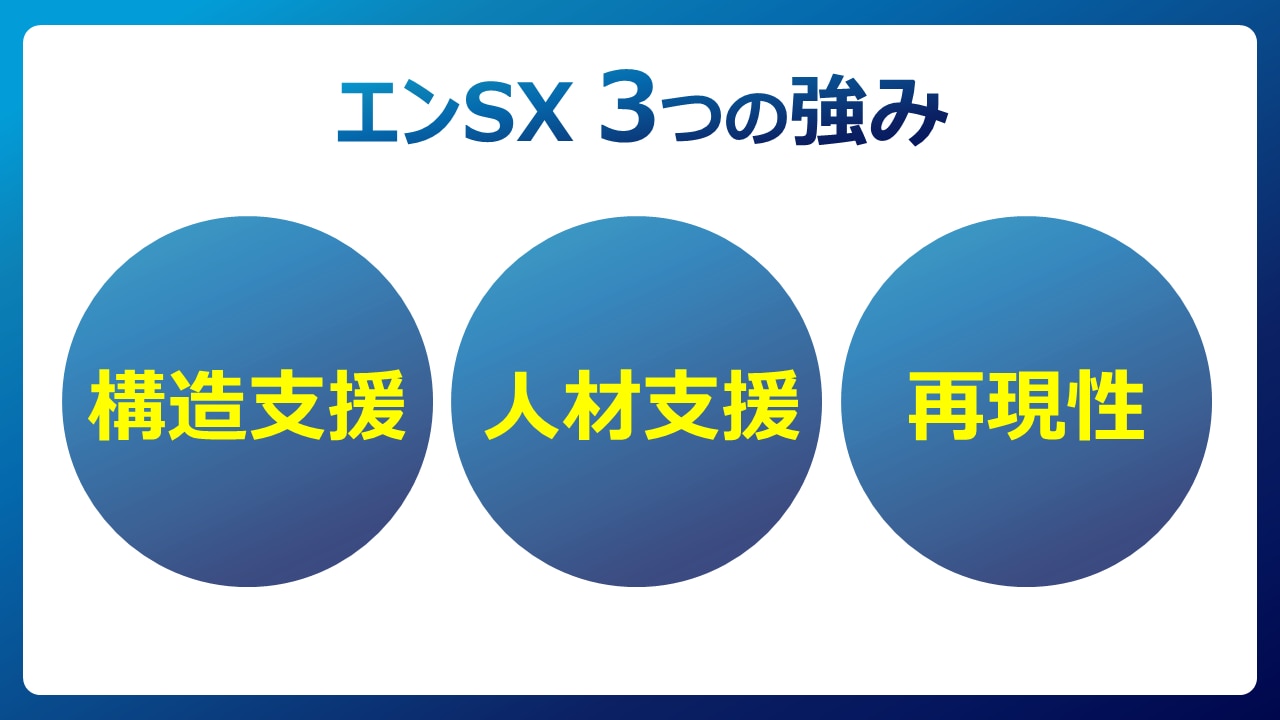
インサイドセールスの導入はもちろん、KPIの設計、CRMを用いた情報共有、さらには内製化 or 外注の判断に至るまで、SIerの営業には仕組み視点での再構築が必要です。
エンSXでは、構造支援+人材支援+再現性のある運用設計を掛け合わせることで、自社に最適な営業体制の実装を支援します。
👉 成果が出るインサイドセールスを始めたい方は、まずはこちらの資料をご覧ください。
インサイドセールス支援サービス資料(無料DL)