
ハウスリストとは?営業効果を高める定義と活用法を解説
「ハウスリスト」とは、過去に接点のあった顧客や問い合わせ、展示会での名刺交換、資料請求、セミナー参加など、自社が独自に保有する顧客情報リストを指します。
特にBtoBの営業現場においては、いきなり新規の架電やメールを行うのではなく、このハウスリストをもとにしたアプローチが、成果に直結しやすいと言われています。
しかし現実には、「どこからがハウスリスト?」「名刺管理とは何が違う?」「どう整理すれば営業に使える?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、営業成果につながるハウスリストの定義・作成・活用法を、インサイドセールスの視点から具体的に解説します。
目次[非表示]
ハウスリストとは?基本定義と重要性
ハウスリストの定義
ハウスリストとは「自社で保有する顧客接点情報」
ハウスリストとは、企業が自社で直接収集・管理している顧客情報のリストを指します。具体的には、過去に商談を行った顧客、名刺交換した取引先、問い合わせをしてきた潜在顧客、イベント参加者など、自社との接点を持った人物や法人の情報が含まれます。
このリストは、第三者から購入したリストとは異なり、企業が自らのマーケティングや営業活動において信頼関係を築きやすい基盤となります。
例えば、2023年の調査によると、日本国内のB2B企業の約75%がハウスリストを活用しており、顧客維持率やアップセル率の向上に寄与していることが報告されています(出典:株式会社マーケティング総研調べ)。
過去の商談・名刺交換・問い合わせ・イベント参加者などが対象
ハウスリストの構成要素は多岐にわたります。具体的には以下のような接点を持つ顧客情報が該当します。
これらの情報は、単なる連絡先以上に顧客の関心度や購入意欲、過去の接触履歴を含むため、営業活動の精度を高める重要な資産となります。
“見込み客リスト”との違いと誤解されやすいポイント
見込み客リストとは、主に外部から取得した「潜在的に興味があるかもしれない顧客」の情報を指すことが多いのに対し、ハウスリストは自社が直接接点を持った相手の情報です。この違いを正しく理解しないと、「見込み客リストをハウスリストと呼んでしまう」などの誤解が生じやすいです。
営業リストとの違いとは?
ハウスリストは「自社との接点あり」、営業リストは「接点なし」
営業リストは、企業が外部から購入したり収集した連絡先の一覧で、自社とこれまで接点のない見込み客情報です。対して、ハウスリストはすでに自社との接触履歴があり、信頼関係構築の土台があることが特徴です。
信頼構築の前提があるかどうか
ハウスリストは顧客との信頼構築の一歩を踏み出した状態であるため、成約率やクロスセルの成功率が格段に高まります。
一般的に、営業リストの成約率は0.5~1%程度とされるのに対し、ハウスリストは3~5%以上の成約率を達成するケースが多いです(参考:営業効率改善協会調査2024年)。
リストの“質”と“温度感”における違い
営業成果に与えるインパクトの比較
▼営業リストの作成方法の作成方法についての記事はこちら
https://sales.en-sx.com/column/no4_sales_list_rule
なぜ今、ハウスリストが重要視されるのか?
新規開拓にかかるコストと労力が高騰している
近年、デジタルマーケティングやオンライン広告の普及に伴い、新規顧客獲得コスト(CAC)は年々上昇しています。例えば、日本のB2B市場においては、2023年時点での新規顧客獲得コストは過去5年で約20%上昇していると報告されています(出典:日本マーケティング協会)。このため、既存の顧客接点であるハウスリストを活用して効率的に売上を伸ばすことが求められています。
情報が豊富な顧客ほど精度の高い営業が可能になる
ハウスリストに蓄積された詳細な顧客データ(購入履歴、問い合わせ内容、興味関心など)を基に、パーソナライズされた営業アプローチが可能です。これにより、顧客のニーズに即した提案ができ、成約率や顧客満足度の向上に直結します。
CRM/MAツール連携によるリストの“価値化”
CRM(顧客関係管理)やMA(マーケティングオートメーション)ツールと連携することで、ハウスリストの情報は単なる名簿から「営業とマーケティングの意思決定を支える戦略資産」へと進化しています。これにより、顧客の行動履歴や反応をリアルタイムに分析し、最適なタイミングでアプローチが可能です。
属人営業から“仕組み営業”への転換が求められている背景
日本企業の多くは、営業活動が特定の営業担当者の経験や人脈に依存する「属人営業」になりがちですが、働き方改革やDX推進の流れで、営業の効率化・再現性向上が急務となっています。
ハウスリストを活用したシステム的な営業プロセスは、営業成果の安定化や組織全体のパフォーマンス向上に不可欠です。
ハウスリストの具体的な作り方
ハウスリストに含めるべき情報とは
基本情報:会社名・氏名・部署・役職・連絡先
ハウスリストの基盤となるのは、顧客や見込み客の基本情報です。以下の項目を正確に把握・記録することが重要です。
日本の営業現場では、2023年の調査で「氏名と連絡先は必須」と回答した企業が98%に達しており、基本情報の充実が営業成果に直結しています(出典:日本営業協会調査2023年)。
接点情報:いつ・どの経路で出会ったか
ハウスリストにおいては、顧客との「接点」が重要です。接点情報の記録により、営業活動の背景や最適なアプローチ方法が見えてきます。
こうした接点情報は、CRM導入企業のうち約85%が「必須項目」として管理しており、営業効率向上に寄与しています。
ニーズ情報:検討状況・課題・興味領域など
顧客の購買意欲や課題、興味関心を正確に把握することは、成約率向上のカギです。ハウスリストに以下の情報を含めることが推奨されます。
2024年のB2B営業動向調査では、ニーズ情報を保有する企業は成約率が平均20%高いとの報告があります(出典:B2B営業研究所2024年調査)。
対応履歴:架電・メール・商談・失注理由など
営業活動の履歴を記録することで、顧客理解の深化と再アプローチの質向上が期待できます。重要な項目は以下の通りです。
ハウスリストの収集元一覧
展示会・ウェビナーでの名刺・参加登録
展示会やウェビナーはハウスリスト獲得の代表的チャネルです。特に名刺交換や参加登録フォームの情報は正確で、接点情報が明確なため貴重なデータとなります。
資料ダウンロード・問い合わせ・サービスサイト経由
Webサイト経由の問い合わせや資料ダウンロードも重要な収集源です。フォーム入力により基本情報とニーズを同時に取得できるため、質の高いリスト構築に寄与します。
営業接触履歴・インサイドセールス活動ログ
営業部門やインサイドセールスの活動ログもハウスリストの重要な情報源です。架電記録やメール履歴、商談メモなど、営業現場のリアルな情報を反映させることで、リストの精度が向上します。
既存顧客からの紹介、担当変更・異動後の再接点
顧客紹介は高信頼度のリード獲得経路であり、また担当者の異動による再接点も新たな営業機会を生みます。こうした情報をハウスリストに組み込むことも効果的です。
Excel?CRM?ハウスリストの管理方法
初期はスプレッドシートでも可:構造設計のポイント
ハウスリストの管理は、初期段階であればExcelやGoogleスプレッドシートでも十分です。ただし、以下のポイントに留意して設計する必要があります。
CRM/SFA導入のメリット(共有・検索・一元化)
企業規模が大きくなったり、顧客数が増えたりすると、Excel管理の限界が見えてきます。その際にCRM(顧客管理システム)やSFA(営業支援システム)を導入すると、以下のようなメリットがあります。
項目設計時の注意点(誰が・いつ・何を見たいか)
CRMやスプレッドシートの項目設計では、「利用者の視点」を常に考慮することが大切です。具体的には、
営業担当者が日常的に確認・更新しやすいか
マネジメント層が営業進捗や課題を把握できるか
マーケティング部門がターゲティングに活用できるか
これらを踏まえた柔軟な項目設計を行うことで、リストの運用効率が格段に向上します。
MAとの連携を見据えた項目分類・タグ設計
近年、マーケティングオートメーション(MA)ツールと連携するケースが増加しています。MA活用を前提としたハウスリストでは、顧客の興味・関心や行動を示すタグ付けや属性分類が重要です。
例えば、
製品カテゴリー別タグ
購買フェーズ(認知、検討、購買)タグ
イベント参加状況タグ
こうした分類により、MAツールでの自動セグメント化やスコアリングが可能になり、営業の質とスピードが大幅に向上します。
ハウスリストを営業成果につなげる方法
インサイドセールスでの活用法
架電対象としての優先順位設定
インサイドセールスでは、限られたリソースを最大限活用するため、ハウスリストの中から架電対象の優先順位を明確にすることが重要です。以下のような基準が一般的です。
2024年の調査では、優先順位設定を導入した企業の約72%が架電通過率が20%以上改善したと報告しています(出典:営業効率化研究所2024)。
過去接点あり→架電通過率/アポ率が高い理由
ハウスリストの最大の強みは、過去に何らかの接点があるため信頼構築の土台がある点です。実際に、
架電通過率は「接点あり」で約65%、新規リストでは約30%(営業データ2023)
アポイント取得率も接点ありリストは約25%、新規リストは約10%前後
と大きな差があります。これは相手がすでに企業名や担当者を認知しているため、心理的ハードルが低いことが主因です。
検討ステージ別のスクリプト戦略
ハウスリストを検討ステージ別に分類し、それぞれに最適な架電スクリプトを用意することが成果向上の鍵です。
ハウスリストを使った“ウォームコール”の実践
ウォームコールとは、既に接点があるリストに対して行う“温かい”架電です。冷たい新規架電と比べて成功率が高いのが特徴で、以下の効果があります。
会話開始時の抵抗感が低い
顧客の反応を踏まえた柔軟な提案が可能
継続的な関係構築が促進される
実践例としては、イベント参加後1週間以内にフォロー架電を行う「即フォロー体制」の構築が推奨されており、これによりアポ率が30%向上した事例も報告されています。
MAツールと連携したリード育成
スコアリング設定:開封・クリック・訪問頻度の活用
マーケティングオートメーション(MA)ツールでは、顧客の行動に応じてスコアリングを行い、ホットリードを抽出します。主要な指標は以下の通りです。
こうしたスコアを基にリードの温度感を判別し、営業に引き渡すタイミングを最適化します。
セグメント別メール配信によるパーソナライズ
顧客の属性や興味に応じたメールセグメント配信は開封率・クリック率の向上に直結します。
反応のあるユーザーを商談化へ繋ぐフロー例
典型的なリード育成フローは以下の通りです。
1.MAで行動スコアリング → 2. スコアが閾値を超えたリードを営業へ通知
→ 3. 営業が個別アプローチ → 4. 商談化
この流れにより、無駄な架電が減り、効率的な商談創出が可能になります。
自動化シナリオと人的アプローチのハイブリッド運用
完全自動化だけでは温かみや顧客の微妙な反応を掴みきれないため、自動配信と営業担当による個別フォローを組み合わせる「ハイブリッド運用」が効果的です。
営業・マーケ・CSをつなぐ共通基盤としての活用
共通データベースによる業務効率の向上
ハウスリストを一元化した共通データベースは、部門間の情報共有を促進し、重複作業や情報の取りこぼしを防ぎます。
米国の調査によると、共通データベースを活用する企業は営業生産性が平均15%向上しています。
リード→商談→顧客→解約リスク管理までの一元化
顧客ライフサイクル全体を管理可能にすることで、アップセルや解約防止施策も効果的に実施可能になります。
一例として、
部門間での“顧客認識のズレ”をなくす
共通基盤を使うことで、営業・マーケティング・カスタマーサクセス間の認識ズレが解消され、顧客に一貫した価値提供が可能になります。
リストベースでのアップセル・クロスセルの企画事例
ハウスリストの詳細情報をもとに、例えば
顧客の利用履歴や導入フェーズを踏まえたアップセル案内メール
同業他社事例を紹介したクロスセルキャンペーン
を企画し、成功している企業も増えています。
▼エンSXでのハウスリストへのアプローチ支援事例はこちら
https://sales.en-sx.com/case/usecase01
ハウスリスト運用でよくある課題と改善策
名刺情報が放置されている
営業個人管理から脱却できない背景
多くの企業で名刺情報は営業担当者の個人管理に依存し、情報共有や活用が進みません。これは
入力工数の多さ
管理ツールの未整備
共有文化の欠如
などが原因です。
情報入力のルール設計と教育方法
効果的な運用には明確な入力ルールと継続的な教育が不可欠です。
名刺管理アプリやOCR連携ツールの活用例
近年、スマホで名刺を撮影し即座にデジタル化できるOCRツールや、名刺管理アプリが普及。これにより入力工数が削減され、精度の高い情報管理が可能となっています。
リストが古く精度が低い
情報の“賞味期限”を意識したリスト設計
リストは鮮度が命。一般的にB2Bリストの有効期限は約6ヶ月〜1年とされ、定期的な更新が不可欠です。
部署異動・退職・企業情報の変化を追う手段
LinkedInや企業Webサイトの定期チェック
専門データベース・外部サービスの活用(例:Teikoku Databank)
などで変化をキャッチアップしリストに反映します。
定期的なクレンジング(整備・削除・更新)の方法と頻度
半年〜1年に1回はリストのクレンジングを実施。重複や退職者情報の削除、連絡先の更新などを行うことで、営業効率を維持します。
使えるリストになっていない
タグ/属性不足でセグメント化できない課題
必要なタグや属性が不足していると、ターゲットに応じたアプローチが困難になります。タグ付けや属性管理は戦略的に設計すべきです。
活用目的から逆算した項目設計の重要性
例えば、「次の商談で提案すべき製品カテゴリーを特定したい」という目的があれば、それに必要な項目(興味分野、検討状況など)をリストに組み込む必要があります。
営業・マーケ・CSでの用途を想定した“使える設計”とは?
部門間で使えるリスト設計は、
営業がすぐ参照できる商談履歴や課題情報
マーケが使う反応履歴や属性タグ
CSが管理する契約情報や解約リスク
が一つのデータベースにまとまっている状態が理想です。
まとめ:ハウスリスト活用の要諦
この記事では、ハウスリストの定義や見込み客リストとの違い、営業成果に直結する活用法までを解説しました。営業効率の改善を目指す中で、「ハウスリストをうまく活用できていない」「情報がバラバラで機能していない」といった課題に直面する企業は少なくありません。
そうした課題に対しては、情報を整理・統合し、“成果に直結する営業プロセス”へと昇華させる「構造的な設計」が不可欠です。属人化せず、再現性のある仕組みを持つことが、持続的な成果を生み出す鍵となります。
“自走できる営業組織”を支える仕組み
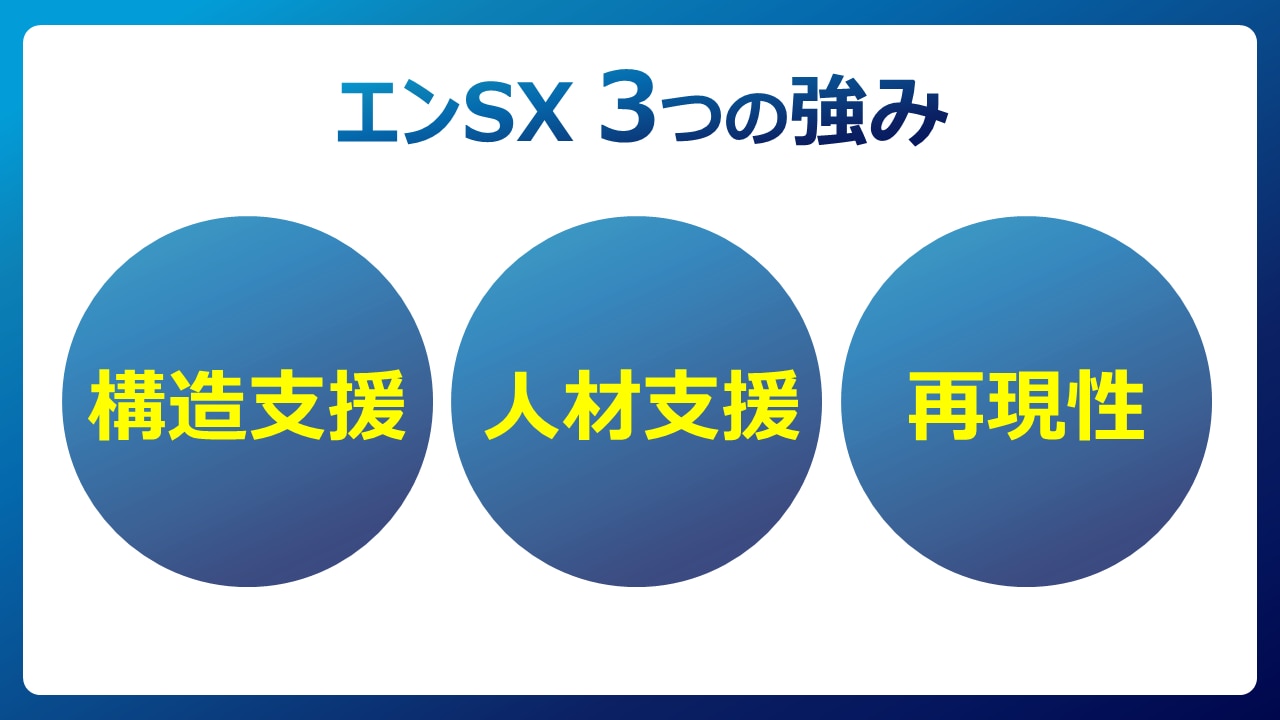
エンSXでは、営業活動の成果を最大化するために、**構造支援(型化)+人材支援(実行)+再現性(仕組み)**の3軸でご支援しています。 体制の立ち上げから改善、内製化まで、貴社の営業課題に応じてカスタマイズが可能です。
まずは無料資料で、どのような支援が可能かをご確認ください。
👉 成果が出るインサイドセールスを始めたい方は、まずはこちらの資料をご覧ください。
インサイドセールス支援サービス資料(無料DL)












