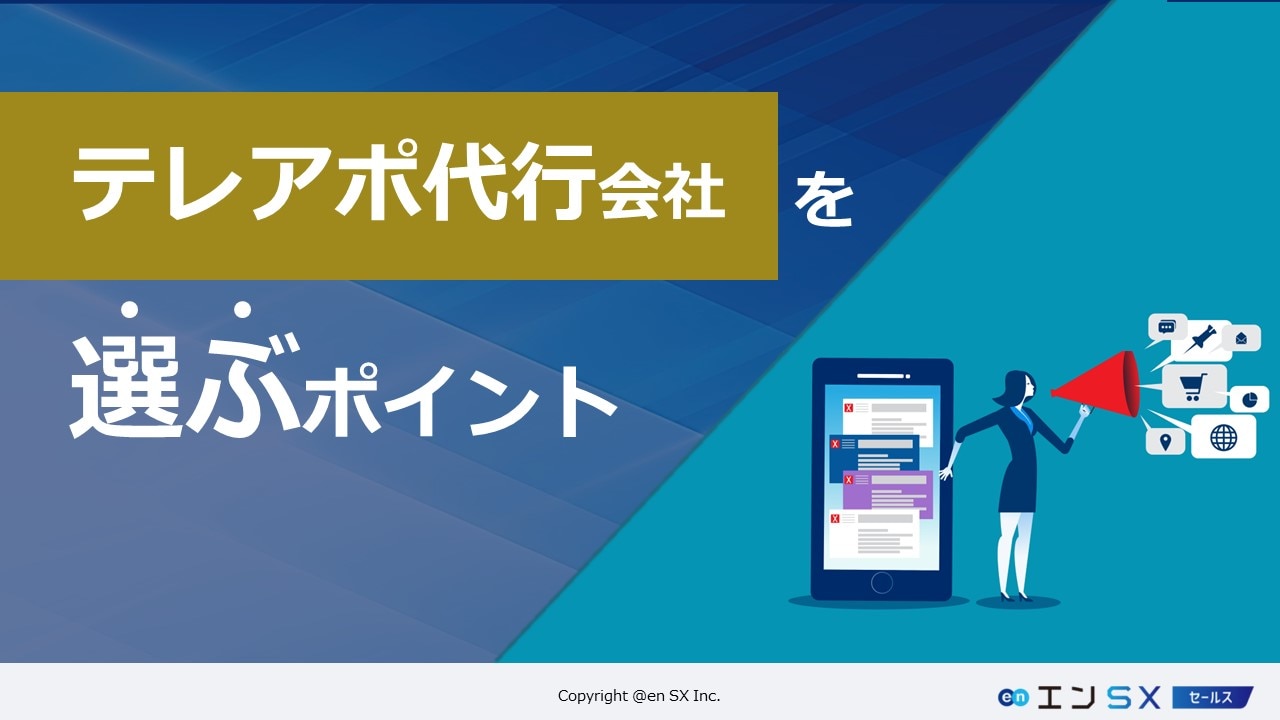展示会営業代行の効果的活用法|成功のポイントと事例解説
展示会で獲得したリードをいかに有効活用し、商談化へつなげるかは多くの企業にとって大きな課題です。営業担当者のリソース不足や属人化が原因で、せっかくの展示会成果が十分に活かせていないケースも少なくありません。そこで注目されているのが、営業代行サービスの活用です。
本記事では、展示会営業代行の役割や導入メリット、効果的な活用法を深掘り。特にインサイドセールスとの連携による成果最大化のポイントや、内製化と外注の判断基準も詳しく解説します。展示会のROIを高めたい企業必見の実践的なノウハウをお届けします。
目次[非表示]
- 1.展示会マーケティングの現状と有用性
- 2.展示会営業の現状課題と営業代行のニーズ
- 3.展示会営業代行サービスの特徴と選び方
- 3.1.営業代行サービスの基本概要
- 3.2.展示会営業代行に求められるスキル・知識
- 3.3.サービス選定時のチェックポイント
- 4.営業代行×インサイドセールスで成果を最大化する方法
- 4.1.役割分担による効率的なリード育成
- 4.2.具体的な運用フローと成功事例
- 5.内製化と外注、どちらが効果的?最適な営業体制の考え方
- 5.1.内製化のメリットと課題
- 5.2.営業代行を外注する利点とリスク
- 5.3.内製と外注の比較表
- 5.4.判断基準とフェーズ別のおすすめ戦略
- 6.まとめ:展示会営業を成果につなぐ鍵
展示会マーケティングの現状と有用性
BtoBマーケティングにおける展示会の位置づけ
BtoBマーケティングでは、展示会は新規顧客獲得や関係構築に重要な役割を果たします。経済産業省の調査では、約65%の企業が展示会を主要なリード獲得手段として活用していることが分かっています。対面での直接接触により、製品理解や信頼形成がスムーズに進む点が強みです。
展示会市場の動向と来場者の特徴
展示会市場はコロナ禍を経て回復傾向にあり、オンライン併用のハイブリッド開催が増加しています。日本展示会協会のデータでは、2024年の出展社数・来場者数はコロナ前水準に近づいており、来場者の約40%が意思決定者という特徴もあります。
展示会がもたらすリード獲得・認知拡大の効果
展示会で得られるリードは質が高く、成約率はオンライン広告の2〜3倍とされています(米国BtoBマーケ調査)。また、来場者の75%が展示会で知ったサービスを社内検討しており、認知拡大にも大きく寄与します。
展示会はコスト面でやや高いものの、質の高い商談機会を得られる点でBtoB企業の重要チャネルです。今後も多様な開催形態を取り入れながら、効果的なマーケティング施策として活用が期待されます。
展示会営業の現状課題と営業代行のニーズ
展示会後のリードフォローでよくある課題
展示会で獲得したリードは多いものの、実際にはフォローが追いつかず商談につながらないケースが多く見られます。営業リソースの不足や対応の属人化、非効率なリード管理が大きな原因です。特に、迅速なフォローが遅れるとリードの興味が薄れてしまい、機会損失に直結します。
営業リソースの不足がもたらす影響
営業担当者が不足すると、獲得リードのフォローが後回しになりやすく、商談成立率が低下します。Salesforceの調査では、リード獲得後3日以内のフォローで商談成立率が約2倍になることが報告されており、リソース不足は直接的に成果に響きます。
属人化による対応ムラと機会損失
営業活動が個人に依存すると、対応の質やタイミングにばらつきが生まれます。結果としてリードの取りこぼしや情報共有不足が発生し、組織としての商談創出力が落ちてしまいます。
リード管理の非効率と情報共有の課題
多くの企業でExcelやメール中心の管理が続き、リードの優先順位付けやフォロー状況の見える化が難しい状況です。これにより、営業とマーケティング間での情報連携が不十分になり、リード活用が最大化できていません。
展示会後リードフォローにおける主な課題と影響
このように、多くの企業が展示会後のリードフォローでリソースや管理面の課題に直面しており、これが商談化率向上の妨げとなっています。
営業代行サービス導入の背景と期待効果
展示会で獲得したリードの迅速かつ効果的なフォローが課題となる中、営業代行サービスの導入が注目されています。営業リソース不足の解消や属人化の防止、さらに営業効率化によるコスト削減を実現できるため、多くの企業が導入を進めています。即戦力としての活用や外部ノウハウの獲得により、営業力強化が期待されています。
即戦力確保によるスピードアップ
営業代行サービスは、経験豊富なスタッフをすぐに投入できるため、自社で新規採用・育成する時間を大幅に短縮できます。展示会直後のリードフォローを迅速に開始できることで、リードの関心を逃さず、成約率向上につながります。Salesforceの調査では、リード獲得後3日以内のフォローで商談成立率が約2倍になることが報告されています。
営業効率化とコスト削減の両立
営業代行を活用することで、自社での人材採用や教育コストを抑えつつ、営業活動の質と量を向上させられます。成果報酬型の契約を選べば、費用対効果を明確にし無駄な支出を抑制可能です。これにより、限られた予算内で効率的に営業体制を強化できます。
営業ノウハウの外部活用メリット
代行サービスには、業界・商材問わず多様な経験を持つプロが多く在籍しており、最新の営業手法やマーケティング戦略を取り入れられます。これにより自社の営業ノウハウが底上げされ、新しいアプローチの導入や改善が促進されます。営業力の継続的な強化にもつながる点が大きなメリットです。
展示会営業代行サービスの特徴と選び方
営業代行サービスの基本概要
展示会営業代行サービスは、展示会で獲得したリードに対して、初期接触から商談化までのフォローアップを専門スタッフが代行するサービスです。営業リソース不足を補い、迅速なリード対応を可能にするため、特にBtoB企業でのニーズが高まっています。サービスによっては、商談同席やクロージング支援まで幅広く対応可能です。
リード獲得から商談化までの代行範囲
営業代行の代行範囲は、主に以下のステップに分かれます。
展示会で獲得したリードへの初期コンタクト(電話やメール)
ニーズのヒアリングおよび案件の絞り込み
商談アポイントの設定
一部サービスでは商談同席やクロージング支援も提供
契約内容や企業の要望により代行範囲は調整可能で、目的に合った最適なサポートが受けられます。
インサイドセールス代行との違い
営業代行サービスは、展示会に特化した短期集中のリードフォローがメインであるのに対し、インサイドセールス代行は既存顧客管理や長期的なリード育成も担います。展示会後すぐの迅速対応には営業代行が適しており、その後の継続的な育成はインサイドセールスが効果的に機能します。両者を連携させることで営業成果を最大化可能です。
成果報酬型と固定報酬型の違い
営業代行の料金体系は大きく分けて以下の2種類です。
展示会営業代行に求められるスキル・知識
展示会営業代行においては、単なる営業スキルだけでなく、業界特有の知識や顧客対応力も求められます。これらがなければ、リードのニーズを正確に把握できず、効果的な商談へつなげることは難しくなります。
広告・マーケティング業界の専門知識
特にBtoB展示会の場合、広告やマーケティング業界に関する専門知識が重要です。商材の特徴や市場動向を理解し、リードの課題やニーズを深掘りできることが、信頼構築と提案力向上につながります。代行スタッフがこうした知識を持つことで、商談の質も大きく向上します。
顧客フォローに必要なコミュニケーション力
リードは展示会直後の接触で興味が高い一方、関心が薄れるスピードも早いため、タイムリーかつ適切なフォローが求められます。そのため、代行スタッフには高いコミュニケーション能力が不可欠です。的確なヒアリングと共感力で信頼関係を築き、長期的な商談成立へと導きます。
サービス選定時のチェックポイント
営業代行サービスを選ぶ際は、単に料金や実績だけでなく、サービスの質や連携体制も重視すべきです。以下のポイントを押さえて選定を行うことが成功の鍵となります。
実績と成功事例の具体的確認方法
過去の導入実績や成功事例を具体的に確認しましょう。業界や商材が自社に近いか、成果指標(商談化率や成約率)が明示されているかが重要です。可能ならば、直接担当者からヒアリングや事例紹介を受けることをおすすめします。
料金体系とROIの具体的な評価方法
料金体系が明確で、自社の営業目標や予算に合致しているかを確認します。成果報酬型か固定報酬型かでコストのリスクやメリットが異なるため、想定されるリード数や商談数に基づくROI(投資対効果)を具体的に試算し比較検討しましょう。
サポート体制や連携方法の重要性
営業代行サービスは自社営業チームやマーケティング部門との連携が不可欠です。情報共有の仕組みや定期的なミーティングの有無、トラブル時の対応体制など、サポートの充実度を事前に確認し、スムーズな協働体制を築けるかを見極めることが重要です。
営業代行の導入を検討中の方へ
営業代行サービスの効果やメリットに関心を持った方にとって、「では実際にどのように会社を選ぶべきか?」は次の重要なステップです。
本資料では、テレアポ代行会社を選ぶ際のチェックポイントを簡潔にまとめています。営業代行を検討する際の参考として、ぜひご活用ください。
👉 資料を無料でダウンロードする(テレアポ代行会社を選ぶポイント)
営業代行×インサイドセールスで成果を最大化する方法
営業活動においては、「リード獲得」から「商談化」「成約」まで、複数のプロセスが存在します。特に展示会などで多くのリードを得た際は、営業代行とインサイドセールスを役割分担することで、より効率的に成果を生み出すことができます。
役割分担による効率的なリード育成
営業代行とインサイドセールスは、それぞれ得意分野が異なります。営業代行はスピーディなリード接触とアポ獲得に強みがあり、インサイドセールスは中長期的なナーチャリングや顧客関係の維持に向いています。
リードの質・優先順位による分類方法
効率的なリード育成には、リードの質(Hot/Warm/Cold)を見極め、優先順位を付けて対応することが重要です。
例えば以下のように分類します。
インサイドセールスとの具体的な連携ポイント
営業代行とインサイドセールスの連携をスムーズに行うためには、以下の3点が重要です:
CRMを活用したリード情報の一元管理
定期的なミーティングによる案件のステータス共有
フェーズに応じた引き継ぎルールの明確化
これにより、リードの取りこぼしを防ぎ、営業プロセス全体の最適化が可能になります。
具体的な運用フローと成功事例
営業代行とインサイドセールスを活用した場合の典型的な運用フローは以下の通りです:
展示会でのリード獲得(マーケティング部)
営業代行がHotリードへ初期アプローチ・アポ獲得
Warm/Coldリードはインサイドセールスが育成
ナーチャリング後、Hot化したリードを再度営業代行または自社営業へ
展示会後のフォローアップタイミング
フォローは「48時間以内」が理想です。展示会後はリードの関心が高まっているため、初動が遅れると競合に先を越されるリスクがあります。Salesforceの調査によれば、3日以内のフォローで商談化率が約2倍に向上すると報告されています。
最適なフォローアップ手法の事例
電話: 関係構築とニーズ把握に効果的(Hotリード向け)
メール: 資料送付や日程調整に活用(Warmリード向け)
MAツール: Coldリードのナーチャリングに有効
これらを組み合わせることで、各リードの状況に最適なアプローチが可能になります。
成功企業の取り組みと成果分析
あるIT企業では、営業代行+インサイドセールス体制を構築し、展示会からのリード800件に対して:
初回アプローチ:営業代行が48時間以内に対応
商談化:3週間で120件(商談化率15%)
成約数:最終的に35件の新規受注(成約率約4.4%)
このように、役割分担とタイムリーな対応が成果に直結しています。
内製化と外注、どちらが効果的?最適な営業体制の考え方
営業活動の実行にあたっては、「自社で対応すべきか」「外部に委託すべきか」の判断が必要です。それぞれにメリットと課題があるため、企業のフェーズや経営資源に応じた選択が成果を左右します。
内製化のメリットと課題
営業ノウハウの社内蓄積と活用
内製化の最大の利点は、営業ノウハウや顧客情報が自社に蓄積され、長期的な組織強化につながる点です。独自の営業スタイルや提案力を育成でき、継続的な改善が可能になります。
採用・育成コストと時間的負担
一方、内製化には人材採用・教育に大きなリソースが必要です。特に人手不足の業界では、スキルを持った営業人材を確保するのが難しく、スピード感のある営業展開には不向きなこともあります。
営業代行を外注する利点とリスク
即戦力の導入とコスト効率化
営業代行を活用することで、短期間で即戦力を投入可能です。採用や教育にかかるコストや時間を省略できるため、初期のスピード立ち上げに向いています。成果報酬型を選択すれば、投資リスクの軽減も可能です。
品質管理の難しさと情報共有課題
一方、外注では営業品質のコントロールが難しくなることがあります。情報共有の不足や、ブランドトーンの統一が取れない場合、顧客体験にばらつきが出るリスクがあります。
内製と外注の比較表
判断基準とフェーズ別のおすすめ戦略
企業の成長段階によって、最適な営業体制は異なります。
スタートアップ期の活用ポイント
スタートアップでは、即効性が求められるため営業代行を活用するのが効果的です。市場反応を素早く得ることで、プロダクトや営業手法の仮説検証をスピーディに回すことができます。
成長期・安定期の体制最適化戦略
成長期や安定期には、内製と外注をハイブリッドで活用するのが有効です。コア顧客対応やノウハウ蓄積は内製化しつつ、リード対応や短期施策は営業代行で柔軟に対応することで、全体の営業効率と成果を最大化できます。
まとめ:展示会営業を成果につなぐ鍵
展示会は質の高いリードを獲得できる貴重なチャネルですが、営業リソース不足や属人化、リード管理の非効率さが商談化の障壁となっています。特に「展示会後のフォローがうまくいかない」という課題は、多くの企業で顕在化しています。
成果を最大化するには、フォロー体制を“属人的な努力”に頼らず、営業プロセス全体を支える構造設計に目を向ける必要があります。
展示会後リードを“成果”に変える仕組み
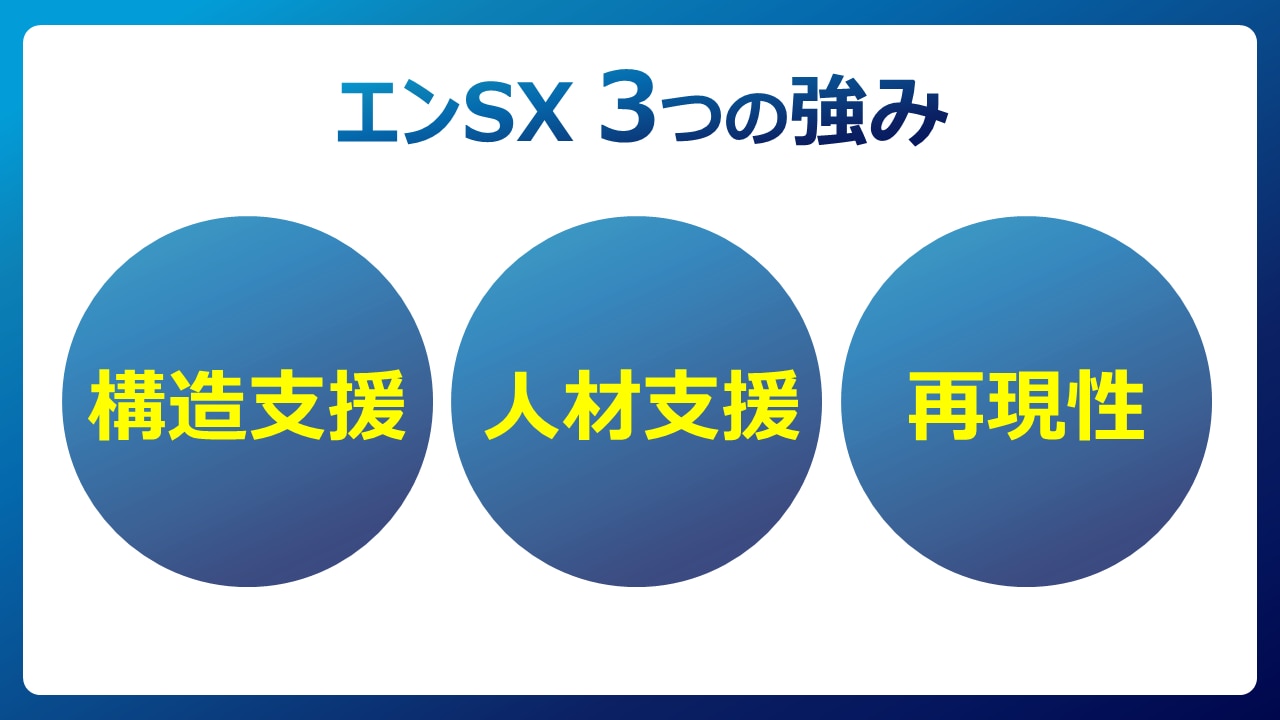
リードの即時フォローと商談化を“仕組み化”することが、展示会営業の成果を左右します。
エンSXは、構造支援(体制構築)+人材支援(即戦力代行)+再現性(標準化と運用設計)により、BtoB企業の営業成果を着実に支援しています。
👉 成果が出るインサイドセールスを始めたい方は、まずはこちらの資料をご覧ください。
インサイドセールス支援サービス資料(無料DL)