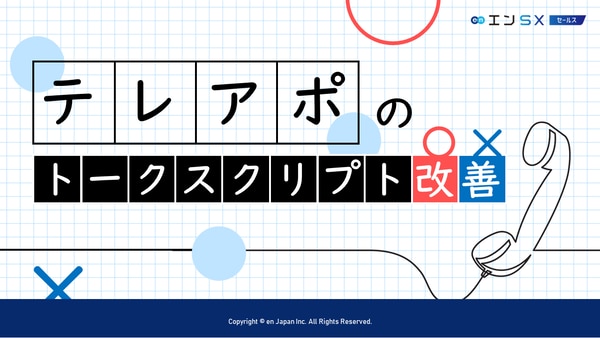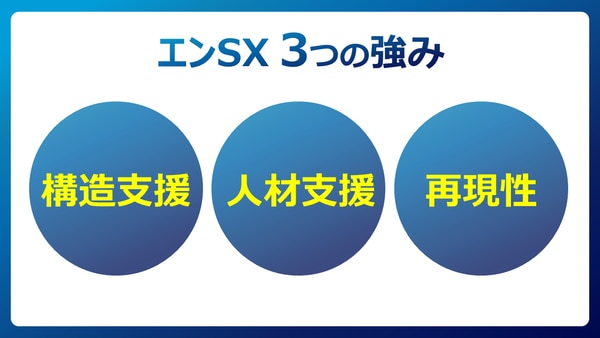インサイドセールス設計の全手順と成功のコツ|設計が重要な理由や成果UPの秘訣も解説

企業の成長戦略において、市場の変化と顧客の購買行動の多様化、そしてテクノロジーの進化などを背景としてインサイドセールスの重要性はますます高まっています。
しかし、
・なんとなくインサイドセールスを導入してみたものの、成果が出ない
・テレアポ部隊と変わらない
・ツールを導入しただけで終わってしまった
といった課題に直面している企業も少なくありません。
その原因の多くは、インサイドセールスの「設計」が不十分であることにあります。
本記事ではエンSXが培ってきた豊富なノウハウをもとに、インサイドセールスの成功に不可欠な設計の手順と、成果を最大化するための秘訣を解説していきます。
目次[非表示]
- 1.インサイドセールス設計の重要性とは
- 2.インサイドセールス設計の7ステップ
- 2.1.ステップ1:目的・目標の明確化とKGI・KPIの設定
- 2.2.ステップ2:ターゲット顧客の明確化とペルソナ・ジャーニー設計
- 2.3.ステップ3:営業プロセスと各部門との連携を定義する
- 2.4.ステップ4:トークスクリプト・メールテンプレートの作成と準備
- 2.5.ステップ5:ツール選定と導入
- 2.6.ステップ6:組織体制の構築と人材育成
- 2.7.ステップ7:運用・分析・改善のPDCAサイクル確立
- 3.インサイドセールスの設計における課題
- 4.自社での設計が難しいと感じたら専門家への相談も
- 5.エンSXなら設計だけでなく運用・改善から内製化までサポート
インサイドセールス設計の重要性とは

インサイドセールスを単なるテレアポの延長線上や、特定のツールの導入で終わってしまい、効果的な成果につなげられないケースが見受けられます。
それらは漠然としたアプローチでインサイドセールスを導入しており、設計が疎かになってしまったことが原因かもしれません。
インサイドセールスを成功させるためには、明確な目的意識と、それに基づいた緻密な設計が不可欠です。
設計がなぜそこまで重要なのか、その理由を掘り下げていきましょう。
数値に基づいた改善ができるようになる
企業成長のためには、さまざまな営業課題を解決する必要があります。例えば、営業活動の効率化、顧客データの有効活用、顧客体験の向上などです。
これらの課題を達成するためには、明確なゴール設定が必要です。そして、そのゴールを達成するためのマイルストーンを具体的に設定し、達成に向けて人材配置や手法を細部にわたって設計することが重要になります。
このような設計ができなければ、営業活動は「勘と経験」に頼ったものになってしまうでしょう。特定の営業担当者の属人的なスキルに依存したり、成果が出ないからといって「人海戦術」のように人材を大量に投入したりするしかなく、いつまでも非効率な状態から脱却できません。
インサイドセールスが適切に設計されていれば、
・架電数
・有効商談数
・商談化率
といった具体的な数値に基づく継続的な改善が可能となります。
どこに課題があり、どのような改善策を講じるべきかが明確になるためです。
効果的な顧客創出が人材不足を解消する
現代のビジネスにおいては深刻な人材不足、特に営業分野での人材育成や熟練者確保の難しさが課題です。インサイドセールスを適切に設計することで効果的な顧客創出ができ、結果的にこの人材不足も解消することにつながります。
インサイドセールス設計によりリードの段階に応じた適切なアプローチが可能になることで、少ない人数で成果を出すことができるため「人数の大量確保」が不要になります。
MAツールで営業プロセスを自動化すれば、さらに少人数で成果を出す営業部隊を作ることも可能です。
また、スコアリングによるリード管理やトークスクリプトの共有・ブラッシュアップによって経験の浅い担当者でも質の高いリード創出が可能となり、営業成果の属人化を防げます。
結果として、少ないリソースで効率的かつ安定的に顧客を創出し続けることができ、指標が明確なため育成もしやすくなることで人材不足の解消につながります。
各段階が噛み合うことでさらに企業成長が加速する
インサイドセールス設計は単なる業務効率化に留まらず、「顧客創出」と「人材不足解消」そして「バリューチェーンの改善と効率化」が噛み合うことで、さらなる企業成長が期待できます。
これは各段階で個別のメリットが生まれるだけでなく、絡み合うことで多岐にわたる相乗効果が発生するためです。
・リード獲得効率の向上によるマーケティング投資のROI最大化
・質の高いリード創出により無駄な営業活動を削減
・リソースを効果的な活動に集中投入することでさらなるシェア拡大
・顧客ニーズのキャッチアップによる商品やサービスへのフィードバック
・非対面活動による訪問や出張にかかる営業コスト削減
・継続的な顧客コミュニケーションによるLTV向上
・アップセル・クロスセル機会の創出
・地理的制約がなくなることによる地方・海外市場への拡大
上記のような、単体でも意義のあるメリットが連携することで相乗効果が生まれ、企業成長を加速させるのです。
インサイドセールス設計の7ステップ

ここまでは、インサイドセールスの設計の重要性について確認してきました。ここからは、インサイドセールスを設計するための7つのステップを具体的に解説します。
これらのステップを踏むことで適切なインサイドセールス体制を構築し、持続的な成果を生み出す基盤を築くことができます。
ステップ1:目的・目標の明確化とKGI・KPIの設定
インサイドセールス設計で重要なのは「どのような結果を目指すのか」という目的設定です。
漠然とした売上向上ではなく、具体的な数値目標を設定することでその後の設計プロセスに一貫性が生まれます。
数値目標が明確になったら、それを達成するためのKGIとKPIを設定します。例えば、KGIが「年間売上20%増」なら、KPIには「月間有効商談数」や「商談化率」などが挙げられます。
具体的なKPIは以下のような指標です。
・架電数
・有効商談数
・商談化率
・アポイント獲得率
・メール開封率・クリック率
・リード獲得単価
これらの指標を設定することでインサイドセールスの活動を客観的に評価し、改善点を発見できます。
ステップ2:ターゲット顧客の明確化とペルソナ・ジャーニー設計
このステップでは、ターゲット顧客を深く理解し顧客視点に立って購買プロセスを詳細に設計していきます。
・誰に、
・何を、
・どのように伝えるか
を定めるステップであると理解すれば良いでしょう。
業界や企業規模などで絞り込んだ後、各セグメントの詳細な「ペルソナ」を作成します。
これは、単なる担当者の性別・年齢・役職だけでなく、課題、ニーズ、情報収集方法まで具体的に描写した架空の顧客像です。このペルソナにより、担当者は顧客をより深く理解し、適切なコミュニケーションを設計できます。
次に、顧客が製品を購入するまでのカスタマージャーニーをイメージし、各フェーズでのインサイドセールスの役割を定義します。
例えば、「課題認識」フェーズでは課題提起を促す情報提供やヒアリングを、「比較検討」フェーズでは自社の優位性を伝えるアプローチを行います。
ペルソナとカスタマージャーニーを深く理解することで、顧客一人ひとりに合わせた効果的なコミュニケーション戦略を構築できます。
ステップ3:営業プロセスと各部門との連携を定義する
インサイドセールスの成果を最大化するには、マーケティングやフィールドセールスなど関連部門との密接な連携が不可欠です。
このため、リード創出から顧客化までの「営業プロセス」と、各部門の役割、連携方法を明確に定義することが重要です。
このステップでは、リードが部門間をどう流れるかを具体化します。
例えば、マーケティングがリードを獲得し、インサイドセールスが育成、商談確度が高まればフィールドセールスへ引き渡すといった流れです。
特に重要なのは、「引き渡し基準」の明確化です。客観的な基準を設定することで、質の低いリードによる工数の無駄や高確度リードの見逃しを防げます。
部門間連携を円滑にするためには、定期的な合同ミーティングで課題や成功事例を共有し、共通のKPIを確認すると良いでしょう。
部門間の連携度合いも人事評価と連携させ、共通の成果によって評価するといった手法で各チーム内だけでなくチーム間の一体感を醸成することが有効です。
ステップ4:トークスクリプト・メールテンプレートの作成と準備
ステップ2で作成したペルソナとカスタマージャーニーに基づき、トークスクリプトとメールテンプレートの作成を行います。
トークスクリプトでは、顧客の課題を引き出すヒアリングのコツを盛り込み、オープンクエスチョンを活用します。そしてヒアリング情報に基づき、製品・サービスの価値提案ポイントを明確に伝え、効果的なクロージングで次のアクションを促します。
メールテンプレートも同様にペルソナとジャーニーを意識し、顧客の興味・関心を引き行動を促す工夫を凝らします。目的やフェーズに応じた複数テンプレートを用意し、件名やCTAを明確にすることで効果を発揮します。
これらのスクリプトやテンプレートは、運用データと顧客反応を分析し、A/Bテストを繰り返しながら継続的に改善することで、インサイドセールスの品質を高められます。
トークスクリプト改善の手法について知りたい方は、こちらより無料で資料をダウンロードできます。
ステップ5:ツール選定と導入
このステップでは、自社の目的や規模に合った最適なツールを選定し、導入を進めます。
これらのツールは、インサイドセールスの各活動を効率化し、データに基づいた意思決定をサポートします。
選定にあたっては、自社のインサイドセールスにおける目的と照らし合わせ、その目的達成に貢献する機能を持つツールを選びましょう。
また、導入時の注意点としては、初期導入費用だけでなく、月額費用や保守費用といったランニングコストも考慮すること、そして何より現場の従業員が使いこなせるか、操作性やUI/UXが優れているかを重視することが挙げられます。
高機能なツールを導入しても、使いこなせなければ意味がありません。導入前にトライアル期間を設けたり、デモンストレーションを受けたりして、実際に使用感を確かめるのがおすすめです。
ステップ6:組織体制の構築と人材育成
優れた設計やツールも、使いこなす人材がいなければ成果は望めません。このステップでは、組織体制や人材育成を設計していきます。
ゼロから立ち上げたり人員を補充したりする場合には、まずはインサイドセールス担当者の採用基準を明確にしましょう。単なる営業経験だけでなく、オンラインでのコミュニケーション能力、傾聴力、分析力など、インサイドセールスに特化したスキルセットを重視します。
採用後は、実践的な育成プログラムを導入します。
・自社の製品知識
・トークスクリプト活用法
・ヒアリング・クロージングスキル
・SFA/CRM/MAなどのツール使用能力
上記について体系的に学習プログラムを設け、ロールプレイングやOJTでスキルを磨きます。
さらに、モチベーション維持と成長を促す評価制度の設計も重要です。商談数だけでなく、リードの質や顧客満足度、データ入力の正確性など多角的な指標を設けます。
育成やそれによる成果向上だけでなく、成果と結びついた明確なキャリアパスを提示することで、メンバーの定着と日々のモチベーション維持につながります。
インサイドセールスに必要なスキルについて知りたい方は、こちらより無料で資料をダウンロードできます。
ステップ7:運用・分析・改善のPDCAサイクル確立
ステップ6までで、基本的にインサイドセールスの設計は完了です。しかしインサイドセールスは、運用開始後も継続的な改善を行うことで真価を発揮します。
運用・分析・改善を行ってさらに成果につなげるため、PDCAサイクルの確立は不可欠なのです。
設定したKGIやKPIに基づき、日次・週次・月次で以下のデータを詳細に追跡します。
・架電数、有効商談数、商談化率
・リード獲得数、メール開封率・クリック率
・各担当者のパフォーマンス
これらのデータはSFA/CRM、MAツールなどを通じて自動的に収集するようにしましょう。
目標と乖離があれば原因を深掘りし、改善策を実行します。例えば、商談化率が低ければトークスクリプトやリードの質の見直し、ヒアリングスキルの検証を行って修正します。
効果を測定しながら次の計画に反映させることで、インサイドセールスは常に最適化・改善されていき、そのノウハウも蓄積されていきます。
KGI/KPIの設定時から後工程で改善することを考慮した設計をしておくのが改善を継続するコツです。
インサイドセールスの設計における課題

インサイドセールスを導入・運用する際、多くの企業が共通して直面するいくつかの課題が存在します。
それらの課題を事前に理解し、あらかじめ適切な対策を講じることでインサイドセールスをよりスムーズに、そして効果的に設計することが可能です。
ここでは、特によくある課題とその解決策について解説します。
部門間の連携不足を解消するには?
インサイドセールスを機能させる上で頻繁に発生する課題の一つが、マーケティング部門とのリード定義のずれや、フィールドセールスへの引き渡し基準の曖昧さといった部門間の連携不足です。
これらの連携不足は、リードの無駄な発生、商談機会の損失、組織全体の非効率性や部門間の軋轢にもつながります。
部門間連携を解消し、円滑なプロセスを構築するためには、以下の要素が重要となります。
・合同MTGの実施
・共通目標の設定
・KGIの共通化
・人事評価との連携(各部門が独自の評価基準を追いかけないようにするため)
これらの取り組みを通じて、各部門が「リードの獲得から顧客育成、そして成約からLTV向上まで」という一連のプロセスを共有し、協力し合う体制を築けるでしょう。
インサイドセールスが部門単体だけで成功することは不可能であると言わざるをえません。
会社全体が一丸となって成果を上げることを仕組み・意識の両面で定着させ、協力しあいながら任された役割を全うするという認識が重要です。
データ活用を進めるにはどうすればいいか?
「SFA/CRMにデータが蓄積されない」「入力ルールが徹底されない」「分析に必要なデータが不足している」といった課題に直面し、データ活用が進まないケースが多く見られます。
このような状況では、データに基づいた効果的な改善策を講じることが困難となります。
データ活用を進めるためには、以下の対策を講じる必要があります。
・入力ルールの徹底(教育や採用も含む)
・ツール活用の推進
・データ分析担当者の育成
インサイドセールスの採用や育成でどういったスキルが必要か?を定義する時点で、上記のようなデータ活用の基礎となる人材を重要視し、評価を高く設定するようにしましょう。
これらの取り組みを実施すれば、データを「入力する」のはもちろん「活用する」文化を醸成し、インサイドセールス活動の質を継続的に向上させることが可能になります。
インサイドセールス担当者の育成が難しく定着しない
インサイドセールスは電話やオンラインでの非対面コミュニケーションが中心となるため、営業活動を担う部門でありながらフィールドセールスとは異なる特性を持ちます。
そのため「モチベーション維持の難しさ」「スキルの属人化」「離職率の高さ」といった、担当者の育成と定着に関する特有の課題に直面する企業も少なくありません。
これらの課題を放置すると、せっかく設計したインサイドセールス体制が機能不全に陥ってしまう可能性があります。
担当者の育成と定着を進めるためには、以下の対策が有効です。
・定期的な研修
・キャリアパスの明確化
・適切な評価制度
・チームビルディング
また、これらの施策を自社で実行することが難しいと感じる場合は、外部に委託することもおすすめです。
専門の代行サービスは人材育成のノウハウを持っており、即戦力となるインサイドセールス人材や育成プログラムの提供を行ってくれます。
これにより、自社でゼロから人材を育成する時間とコストを削減し、安定したパフォーマンスを確保することができるでしょう。サービスによっては内製化支援までしているところもあるので、最終的な着地点を想定しつつ自社に合った手法を選択することが重要です。
自社での設計が難しいと感じたら専門家への相談も

インサイドセールスの設計は多岐にわたる専門知識と豊富なリソースを必要とするため、自社だけで全てを完結させるのは容易ではありません。
特に短期間での成果創出や専門性の高い組織構築を目指す場合、自社での設計・運用には限界を感じることもあるでしょう。
このような状況において、外部の専門家や代行サービスを活用することは有効な選択肢となります。
外部の専門家・代行サービスを活用するメリット
外部の専門コンサルタントや代行サービスを活用することで、彼らが持つノウハウ、実績、そして豊富なリソースを活用し、スピーディーに成果を出せるという大きなメリットがあります。
例えば、以下のような具体的なメリットが期待できます。
・即戦力となる専門性の活用
・時間とコストの効率化
・客観的な視点からの課題特定と改善
・最新トレンドと技術の導入
・浮いた自社リソースをコア業務へ集中
このように外部の専門家や代行サービスの活用は、インサイドセールスの成功を加速させるだけでなく、企業の成長戦略を後押しする選択肢となり得るのです。
設計を専門家に依頼したほうがいい企業とは
インサイドセールスを外部に依頼することのメリットは理解しつつも、失敗してしまう可能性を感じる企業も少なくありません。
当然ながら、やみくもにどんな企業でも外部委託して成功するわけではないのです。一方で、明確に「依頼したほうがメリットが多い」といえる企業も存在します。
特に以下のような状況に当てはまる企業は、外部の専門家や代行サービスへの依頼を検討することをおすすめします。
・人的リソースが足りない
・マーケティング、営業戦略、データ分析、ITツールに関する専門知識がない
・中長期計画ではなく早急かつ短期的に成果を出したい
・セールス以外のコア業務(プロダクト開発など)に集中したい
上記のようなケースに当てはまる企業は、インサイドセールスの専門家に相談することをおすすめします。
ただ単に営業部門の再構築やインサイドセールス設計の枠を超えて、企業としての戦略にも良い影響を与える可能性があるためです。
エンSXなら設計だけでなく運用・改善から内製化までサポート
ここまでインサイドセールス設計の重要性と、各ステップのポイントを解説してきました。
セールスは単なるテレアポやツール導入ではなく、綿密な戦略と継続的な改善を伴うことで初めてその真価を発揮します。
本記事で解説してきた設計プロセスはあくまで一般的なステップであり、業界特性、事業規模、組織文化、そして具体的な経営課題によって、最適な設計は大きく異なります。
エンSXは、エングループが蓄積してきた「企業活動に関する知見」と「人材」というアセットを強みとしており、以下のようなさまざまな支援が可能です。
・ターゲット顧客の分析
・最適な営業プロセスの構築
・効果的なトークスクリプトやメールテンプレートの開発
・最適なツールの選定と導入支援
・インサイドセールス担当者の採用・育成プログラムの提供
・貴社内でのインサイドセールスチームの内製化
もしインサイドセールスの導入を検討している、あるいは現在のインサイドセールスの成果に課題を感じているのであれば、ぜひ一度エンSXにご相談ください。貴社のビジネスを加速させるための最適なインサイドセールスを、私たちと共に設計していきましょう。