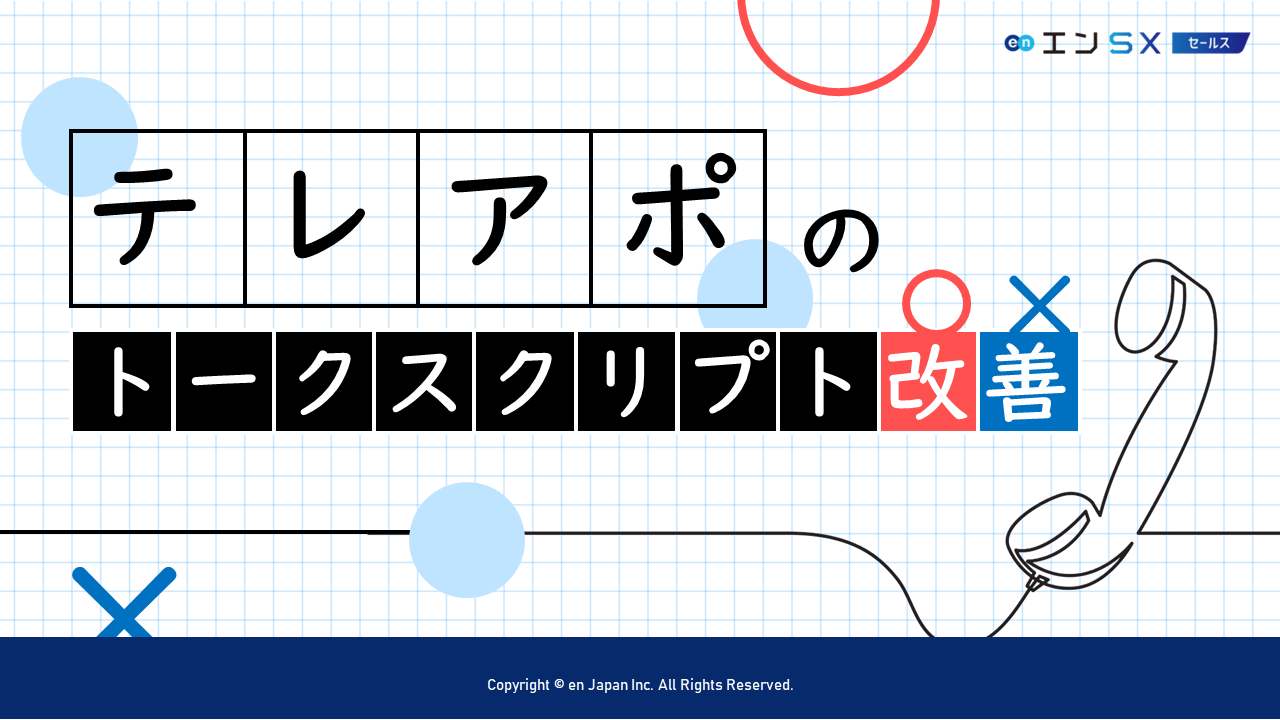営業で断られない!応酬話法とは?実践例と成功の型を解説
インサイドセールスやフィールドセールスなど、BtoB営業において頻繁に直面するのが「お断り」や「反論」です。例えば、「予算がない」「検討中です」「今はタイミングではない」など──そのまま引き下がれば、商談や受注のチャンスを逃してしまいます。
そこで必要になるのが「応酬話法」。
これは、相手の反論や懸念を受け止めつつ、会話を前向きに進めるためのトーク技法です。
本記事では、応酬話法の定義から、具体的な型、反論対応の例文、注意点、現場での応用までを体系的に解説。ただの知識にとどまらず、「成果を出す営業トーク」に昇華させるための実践ノウハウをお届けします。
目次[非表示]
応酬話法とは?営業で求められる理由
営業現場で「応酬話法」が求められる理由は、顧客からの「拒否」や「疑問」への対応を通じて会話を前に進め、商談成立につなげるためです。実際、営業アクションの中で以下のような人数・割合が見られます。
※¹:インサイドセールス実務者への聞き取り調査による平均値
※²:某BtoB企業によるA/Bテスト結果より(応酬話法を学習したグループと未学習で比較)。
これにより、営業パーソンは単なる返答だけでなく、会話を建設的に導くスキルが不可欠とされるのです。
応酬話法の定義と目的
応酬話法の定義(反論対応の技法)
応酬話法とは、顧客から投げかけられた「疑問」や「懸念」、「拒絶」を受け止めながら、以下のような段取りで対応するコミュニケーション技法です。
共感:まずは「おっしゃる通りですね」と顧客の言葉に理解を示す。
再定義:「そのご懸念は〇〇とも言えますが、△△という観点もございます」など、
同じ現象を別角度で提示。
具体提案:「例えば、~のような導入事例では□□のように解決できています」など、
解決シナリオを伝える。
この段階を踏むことで、単なる言い返しや否定反論とは異なり、顧客との信頼関係を維持しつつ、会話を「前進」させることが可能となります。
営業活動における応酬話法の目的
応酬話法の目的は大きく以下の3つに分類できます
実際の営業現場では、応酬話法を用いることで、初回商談からクロージングまでの移行率が平均で10%以上向上するケースも報告されています。
ただの言い返しではない「前進する会話」の重要性
応酬話法が真に意味を持つのは、相手を否定するのではなく、対話を“前進させる”点にあります。
例えば、相手から「予算が高すぎる」と言われた場合
ただの言い返し:「それは違います!費用対効果が高いです!」
応酬話法:「ご指摘の予算感、ごもっともです。ただ、同じ規模の他社では導入後6ヶ月で
ROIが120%に達したという結果も出ており、コスト以上の価値をご提供できる
可能性があります」
このような構成を通じて、相手の理解を得つつ前向きなコミュニケーションを促すのが、本来の応酬話法の本質です。
BtoB営業で「断られる」瞬間とは?
よくある断られポイント(アポ時、初回商談、クロージング前)
BtoB営業において、“断られる”瞬間は主に以下の3フェーズに集中します
*自社営業データおよび業界平均に基づく参考値。
上記フェーズでの“断り”に応酬話法を使うことで、再検討や再商談につなげる確率が格段に高まります。
インバウンド営業とアウトバウンド営業の違い
たとえば、インバウンド営業では「競合との差がわからない」という反論に対し、「競合Aでは機能Xに弱い一方、弊社ではYという機能を強化しています」と応える応酬話法が効果的。一方、アウトバウンド営業では、「そもそも話を聞いてもらえない」ことが多いため、「少しお耳をお借りできれば、御社の〇〇の課題解決にご参考になるお話がございます」などの導入が鍵となります。
断りの裏にある「本音」と「建前」
顧客の「断り」には、表層にある“建前”と、本音とが入り混じっています
こうして、本音に近づく質問や提案を挟むことで、建前以上の会話進展が期待できます。
インサイドセールスにおける応酬話法の役割
SDR/BDRなど営業プロセスでの位置付け
インサイドセールス(SDR/BDR)のミッションは、商談化に向けた関心喚起とアポイント獲得です。このフェーズでは、応酬話法は以下のような位置付けとなります
アポ取得時:「今は忙しい」と言われた際にも、「お忙しい中恐縮ですが、10分だけ
でも△△について差し支えなければご説明させて頂く価値がございます」ニーズヒアリング時の疑問対応:「同業他社では~」という反論に、「確かに多くの
企業様も同じ問題を抱えていらっしゃいましたが、
弊社の導入事例では…」という流れで信頼を築く。
このように、途中で対話を止めさせず、商談成立への道に誘う役割を果たします。
MQL〜SQL転換で活きるトーク力
マーケティングリード(MQL)からセールスリード(SQL)へ転換する際は、以下の数値にも注目。
MQL→SQLへの転換率(業界平均):約25〜35%
応酬話法活用による改善額:+5〜10%ポイント※³
※³:某CRMベンダーが営業チーム全体で実践した改善結果より。
具体的には、見込み顧客から
「今はまだ比較段階です」
「社内で検討体制が整っていません」
などの反論に対し、応酬話法で対応することで、SQL化率の向上に直結します。
【無料DL】実践で使える「テレアポのトークスクリプト改善」資料
現場で成果を出す応酬話法を、ただ知識として終わらせず、日々の営業トークにどう落とし込むかが成果の分かれ目になります。
特にインサイドセールスやアポ獲得においては、「トークスクリプトの設計」が応酬話法の効果を最大化する鍵です。
営業の“型”を仕組み化し、成果につなげたい方は、まずこちらの資料をご覧ください。
👉 テレアポのトークスクリプト改善資料を無料でダウンロードする
ファーストコンタクトで印象を左右する技術
ファーストコンタクト(メール/電話/Webミーティングの初回)では、以下の点が印象の分かれ目になります。
こうした応酬話法的な言い回しを用いることで、第一印象から信頼感と共感を醸成し、以降の対話をスムーズに進める土台が整います。
よくある断り文句と反論パターン
営業の場で頻繁に出てくる“断り文句”にはある共通点があり、それぞれに適切な「反論パターン(切り返し)」があります。ここでは代表的な断り例を挙げ、それぞれの背景と反論例を整理したうえで、心理的要因を掘り下げます。
代表的な「断りフレーズ」一覧
営業現場でよく耳にする断りフレーズと、それぞれの典型的な対応パターンを以下の表にまとめます。
「予算がない」と言われたときの対応
背景
「予算がない」という断りは、最もよく使われるものの一つです。建前としては“予
算編成が終わっている”“他件に予算が割かれている”などがありますが、本音とし
ては「その支出見合いの効果を信じていない」「他の投資優先順位が高い」「費用
負担の心理的抵抗」が隠れていることが多いです。
反論パターン(切り返し例)
共感を示す → 「確かに、予算の問題は多くの企業様で大きな懸念事項です。」
まずどの部分で「予算がない」と感じているかを確認する質問 →
「導入費用ですか、それとも運用コストが将来的に重くなりそうだからでしょうか?」効果を数字で示す → ROI、コスト削減率、他社の事例など具体数値を用いて
価値を裏付ける。支払い条件や導入モデルの提案 →
分割払い、段階導入、スモールスタート(小規模導入)などで負荷を下げる。「投資」ではなく「コスト削減/利益創出」と位置づけ直す →
長期で見たトータルコスト、利得、または失われる機会コストを可視化する。
例文
「ご予算のご懸念、理解いたしました。もしよろしければ、どのような予算感を想定されていたか、また導入された場合どれくらいメリット(コスト削減・業務効率化など)をご期待されているかをお伺いできますでしょうか? トライアル的にスモールスタートのプランもございますので、初期投資を抑えてご評価いただくことも可能です。」
「決裁者がいない(確認する必要がある)」
背景
建前:その人には判断できない/上司の承認を得る必要がある。
本音:決裁者へのアクセスが困難、決裁者が前向きでない可能性、
内部合意形成プロセスが曖昧で時間がかかることを恐れている。
反論パターン
誰が最終的な決裁者かを丁寧に確認 →
「御社では、このような決定はどの方がされますか/どの部門になりますか?」決裁者が重視する基準をヒアリング → コスト、ROI、他社導入実績など。
決裁者に対する資料や提案をサポートする →
上司向けの資料を準備する、プレゼンの同席を提案するなど。決裁プロセス・スケジュールを明らかにするヒアリング →
「この提案を上げるのにどれくらい時間がかかりますか?」など。
例文
「ありがとうございます。失礼ですが、そのような案件について最終的に意思決定をされる方はどなたになるのでしょうか? もしよろしければ、○○さんが上申されるにあたって、その方に響くポイントを中心に資料をまとめてご準備いたします。」
「他社と比較中(検討中)」の背景にある懸念
背景
建前:慎重な検討姿勢を示す。
本音:比較対象に自社との違いが見えていない、
製品/サービススペック・サポート・価格・信頼性などで不安。また、過去の経験から“比較ばかりで決まらない案件”となってしまっている恐れ。
反論パターン
他社を使っていて良い点・不満な点を聞き出す →
差がつけやすいポイントを見極める。自社の強み・独自性を具体的に示す →
他社がカバーしていない課題やサービスを明示。比較材料を提供する → ケーススタディ、サイドバイサイド比較表など。
無料トライアルやデモ・実証導入などで比較しやすくする提案。
例文
「比較検討されているとのこと、承知いたしました。他社様との違いを把握されていらっしゃるものも多いかと思うのですが、もしよろしければ現時点で他社様に対してどの点が良いと思われていて、逆に不便だと感じている点があるかお伺いできますか? そのうえで、御社にとって最も価値のあるところを、弊社の導入事例も交えてご紹介したいと思います。」
「今はタイミングじゃない」と言われたとき
背景
建前:年度末・予算期で動けない、他プロジェクトが優先。
本音:変化に対する心理的抵抗(現状維持のバイアス)、
自分が動き出す理由を見いだせていない、リスクをとりたくない。
反論パターン
「いつ頃ならご検討可能でしょうか?」など具体的なタイミングを探るヒアリング。
「なぜ今はタイミングが悪いのか」を掘る →
スケジュール/予算/社内プロセスなど。将来的に起こりうるコスト・機会損失を伝える。
小規模導入やパイロット案件で“今できること”を提案。
例文
「そうですよね。そのご意見、よくわかります。もしよろしければ、御社で“動きやすいタイミング”はいつ頃になりそうかをお聞かせください。また、今先に動いておくことで将来コスト削減やリスク回避につながる点もいくつかございますので、それについても簡単にご説明させていただければと思います。」
「興味はあるが必要性を感じていない」
背景
建前:前向きな姿勢を見せつつ、実際には自社の“痛み”や課題が弱いため、
あまり変えたくない。本音:リスク回避、変化への抵抗、現状で困っていない
という錯覚(現状維持)。
反論パターン
現状における「困っていること」「非効率な部分」のヒアリングを深める。
現在の状態が持続不可能な場合や将来どうなるかを可視化する。
過去の成功事例で、似た業界/似た業務で“必要性を感じなかったが
入れて良かった”ケースを示す。小さなテスト導入や限定機能でまず使ってもらう提案。
例文
「興味をお持ちいただいているとのことで嬉しいです。もしよろしければ、今御社で業務を進める上で“手間を感じていらっしゃる箇所”や「もう少し効率が良くなったらいいなと思うところ」があれば教えてください。それらをもとに、どれくらい改善可能か具体的数字でシミュレーションしてみます。」
「過去に使ってうまくいかなかった」
背景
建前:過去の導入経験を根拠にする。
本音:不満があった、信頼性やサポート体制、使い勝手などで失望した経験が
あるため、新しい提案にも慎重。
反論パターン
どの部分が「うまくいかなかったか」を具体的に聞く。
機能・サポート・定着/教育など。過去とは異なる点を示す → 技術・サービス体制・改善点。
デモやパイロットを提供し、実際に体感してもらう。
保証制度や導入後フォロー・返金対応などリスク軽減のオファー。
例文
「そういったご経験をされたとのこと、貴重なお話ありがとうございます。差し支えなければ、どの点で“うまくいかなかった”と感じられたのかを教えていただけますか? 弊社ではその点を改善して~という対応を取っておりますので、それを中心にご説明させていただきたいと思います。」
反論の裏にある心理とは?
断り文句の背後には、顧客の心理があり、それを理解できれば応酬話法で適切に対応できます。以下、主要な心理メカニズムを整理します。
リスク回避の心理(現状維持バイアス)
内容:人は「現状が無難」と感じると、不確実な変化を避けたくなる傾向があります。
特にコストや組織変更、プロセスの変化などは“損失”と感じられやすい。影響:新しいソリューションの検討は“リスク”と捉えられ、断り文句として
「必要性を感じない」「今はタイミングじゃない」などが出やすい。対応策:変化による“負担”を小さく提示する。既存との比較で“変えるメリット”と
“維持するコスト”を明確にする。
コントロールされることへの抵抗感
内容:営業側から強くアプローチされると、
「押し付けられている」「選択肢が制限されている」と感じることがあり、
反発が生まれる。影響:「決裁者がいない」「検討中」などの表現で、
自ら断る余地を持ちたい心理が働く。相手に主導権を感じさせたい。対応策:選択肢を示す/対話型のヒアリングを行う/
相手が決められる部分を残す表現を使う。
(例:「○○様がお決めになる基準は何ですか?」など)
本音を探るための「仮の反論」の可能性
内容:「予算がない」「役員の確認が必要」などの文言が、本当の理由ではなく、
表層的な言い訳であることが多い。これを“仮の反論”と呼ぶ。影響:営業側がそのまま受け取ってしまうと、次のステップに進めない。
裏にある本当の痛みや懸念を見つけられないと、成約に結びつかない。対応策:質問を重ねて本音を引き出す。例:「もし予算が厳しいとしても、
この機能だけなら対応可能か」「過去の経験で不満だった点はどこか」など。
相手の業務状況や上司の目を意識した発言
内容:特にBtoB営業では、担当者が“評価”される立場にあり、
「上司からどう思われるか」「社内稟議で追及されないか」などが気になる。
これが断りの言葉に影響する。影響:「決裁者がいない」「他社比較中」などは、
この評価・責任回避の意味を含むことがある。対応策:責任を軽減する提案をする。
上司や理事会向け資料を用意する/定義された評価指標で成果を示す/
相談しやすくする環境をつくる。
成果を出す応酬話法の「型」とは?
応酬話法には、状況や顧客心理に応じて使い分けることが重要な“型”があります。以下では代表的な3つのフレームと、その選び方や場面別の適用例、NG/OK例を通じた実践的な理解を図ります。
基本フレーム3選(Yes but 法 / クッション話法 / PREP法)
Yes but 法(共感→逆提案)
構成:
Yes(共感・受容):相手の言い分をまず認める。
But(逆提案・理解の上で価値提示):ただしその視点を補足・再定義する提案を行う。
特徴:
顧客の疑念や抵抗を柔らげつつ、自分の主張も伝えるバランス型。
先に共感を示すことで防御反応を和らげる効果が高い。
例:
「ご予算についてのご懸念はごもっともです。ただ、〇〇社では導入後3ヶ月でコストを20%削減できており、初期投資の回収が見込まれています。」
クッション話法(受け止め→主張)
構成:
クッション(受け止め):「~という点、承知いたしました」と相手の言い分を受ける。
主張:その上で、自社の見解や提案に移る。
特徴:
相手の発言にしっかり “聴きました” を伝えたうえで、
自分の考えを提示するため、対話がスムーズ。防衛的な反応を抑える効果がある。
例:
「確かに、御社では過去に導入されたことがあるとのこと、承知しました。その経験を踏まえ、今回のご提案ではサポート体制を強化し、運用の定着を確実にする仕組みを付加しております。」
PREP法(Point‑Reason‑Example‑Point)
構成:
Point(結論):まず主張を簡潔に述べる。
Reason(理由):なぜそれが正しいのか理由を述べる。
Example(具体例):実例や数値で裏付ける。
Point(再結論):再度主張を強調。
特徴:
ロジカルで説得力ある構成。特に意思決定層へのアプローチに有効。
数値や事例の裏付けによって信頼性が高まる。
例:
・Point:「このソリューションの導入は御社の業務効率向上に寄与します。」
・Reason:「なぜなら自動化により作業時間が30%削減できるからです。」
・Example:「実際、A社では導入後、月間作業時間が100時間から70時間に減
少しました。」
・Point:「つまり、業務改善と時間の節約を確実にもたらします。」
応酬話法の構成要素と選び方の基準
応酬話法における効果的な構成要素と、どの型を使うべきかの目安を下表にまとめます。
型の選び方の基準:
相手が拒否的・慎重な場合 → Yes but 法 や クッション話法 が効果的。
論理的・数字重視の意思決定者には → PREP法 が有効。
営業での使い分け方
営業の"いつ・誰に・どう"応酬話法を使うか、場面別・顧客タイプ別に整理します。
ヒアリングフェーズでの応酬
目的:相手の本音や課題を引き出すため、反論というより対話を深める段階。
使う型:クッション話法が最適。相手の意見にゆったり寄り添いながら、
本音を聞き出せる。
例:
「そうでしたか、そのようなお考えをお持ちなのですね。もう少し詳しく、現在どのような点に一番お困りかをお聞かせいただけますか?」
提案フェーズでの応酬
目的:顧客の懸念(予算/比較中/過去不成功など)に対して納得性高く応じる。
使う型:Yes but 法 または PREP 法。
例(Yes but):
「おっしゃる通り、予算へのご懸念はごもっともです。ただ、〇〇の改善により△△%のROIが見込める例もございます。」
クロージングフェーズでの応酬
目的:最後の懸念(決裁者・タイミングなど)に対応し、決断を促す。
使う型:PREP 法が効果的。結論強調+根拠提示で背中を押す。
例:
・Point:「ぜひ今月中にご決断いただければ、初期導入サポートを無料で追加
提供できます。」
・Reason:「御社の立ち上げフェーズでサポートがあると定着率が高まりま
す。」
・Example:「導入A社では、この支援により初月解約率が50%下がりまし
た。」
・Point:「ですので、今ご契約いただくことに大きな意義があります。」
顧客タイプ別(慎重派・決裁重視・価格重視など)
実践的トーク例(NG例とOK例の比較)
具体的な断りへの応酬トークを、NG例/OK例で比較します。
「予算がない」への NG/OK トーク比較
「検討中」への NG/OK トーク比較
「導入済み」への NG/OK トーク比較
(=「過去に使ってうまくいかなかった」背景を踏まえたケースと重なる部分があります。)
すぐに現場で使えるテンプレ集
以下、応酬場面別に即使用可能なテンプレートをまとめます。
応酬話法を効果的に使うためのポイント
応酬話法をただ知っているだけでは十分ではなく、「どのように使うか」が成果を左右します。ここでは、応酬話法を使いこなすための3大流れ、避けるべきNG行動、商談フェーズ別での実践ポイント、という観点で整理します。
共感 → 質問 → 提案の流れを意識する
応酬話法で最も成果が出るのは、相手との対話の流れを意図的に“共感 → 本音を探る質問 → 課題解決へ結びつける提案”の順で構成することです。
まずは受け止める(共感・同調)
相手の不安・否定的発言を無理に否定せず、まずは理解を示す表現を使う。
例:「おっしゃる通りです。△△というご懸念、よくわかります。」共感を示すことで相手の防御心を下げ、聞く姿勢を作る。
人はまず「聞いてもらえている」と感じることが重要。実践では、「肯定法」「バックトラッキング」がこの段階で用いられることが多い。
例えば「そうですね」とか「なるほど、その点は確かに…」という表現。
本音を探る質問を投げる
共感の後、表面的な断り・建前だけで終わらせず、どの部分が本当にネックなのかを
探るための質問をする。例:
「予算がない」というお話ですが、どの程度の予算枠を想定されていたか
お聞かせいただけますか?
「他社と比較中」とのことですが、比較対象で特に重視されている点は何でしょうか?質問はなるべくオープンエンド(「なぜ」「どのように」)型を用い、相手が自由に
話せるようにする。これにより、隠れた懸念や過去の体験、決裁プロセスなどが
見えてくる。SPIN話法などのヒアリングフレームがこのフェーズの強力なツールとなる。
課題解決につながる提案に導く
本音を聞き出したあとは、相手の懸念や状況に合わせた提案を行う:
回答するべき懸念を整理
提案内容を相手のニーズにリンクさせる
数字・実例を交えて信頼性を高める
提案は“変化後のメリット”を明確に伝える。
「何を改善できるか」「どれくらい効果があるか」を具体的にすることが肝心。また、提案する際に複数の選択肢を用意することで、相手に“選ぶ自由”を与え、
コントロール感を保たせる。
反論対応における NG 行動(説得・押し売り・否定)
応酬話法で成果を出すには、「してはいけないこと」を知るのも重要です。以下が、代表的な NG 行動とその理由、回避の方法です。
「説得しよう」とする態度の危険性
説得を強めすぎると相手が防御反応を起こし、
「押し切られるようだ」「自分の意見を聞いてもらっていない」と感じられる。会話が一方通行になり、関係性が悪化する。
相手が「ノーと言いにくい状況」に追い込まれると、後から後悔されることも。回避策:相手の言い分を聞き、共感を示す → 提案は選択肢として提示する →
相手の反応を見ながら柔らかく修正する。
「押し売り」にならないための空気感
押し売りと判断されるのは、営業が「今日決めてほしい」「この話を逃すと損ですよ」
と急かすような言い方をする時。限定感や緊急性を過度に強調するのもその一因。また、相手の疑問や断りを遮って話を進める「強引さ」も印象を悪くする。
回避策:話すペースを相手に合わせる/クッション言葉を使う/選択肢を与える/
決断のタイミングを相手に持たせる。
「否定」は信頼関係を崩す最大要因
相手の発言を即座に否定したり「それは違います」と切り替えると、
相手は聞く耳を閉じてしまう。心理的に「否定された → 防衛態勢」に入るため、
以降のトークが入りにくくなる。初動で否定しないこと。共感を持ち、一旦受け止めたうえで、
必要あれば再定義や修正を提案する形で話を進める。
商談フェーズ別での使い方(初回接触〜クロージング)
商談のフェーズによって、相手の期待・心理・情報量が異なります。それぞれに応じて応酬話法を使い分ける必要があります。
初回接触時の反論にどう対応するか
典型的な反論例:「今忙しい」「少し興味はあるが」「後日連絡ください」など。
対応ポイント:
1.共感:「お忙しい中のお時間、ありがとうございます」
2.質問:「差し支えなければ、いつ頃でしたらお話しできるタイミングがよ
ろしいでしょうか?」
3.提案:「5分ほどで要点のみお伝えできますので、ご都合のよろしい時間を
調整いたしましょうか?」
効果として、初回接触の折返しのアポイント取得率が上がる。準備しておいた
切り返しトークを持つと良い。
ヒアリング中の懸念を潰す方法
ヒアリングフェーズでは相手の課題や懸念をあえて引き出すこと。質問を通じて本音を探る。
例えば:「現在の仕組みで何か手間を感じていらっしゃるところはありますか?」、
「これまでこのようなツールを導入された際に苦労されたことはございますか?」など。引き出した懸念をその場でクリアできるものはその場で応える。応えられないものに関しては
「この後の提案でその点もしっかり考慮したいと思います」と伝えることで信頼を保ちつつ
提案フェーズに進む。
提案後の反論は「受け入れ + 再提示」が基本
提案内容を説明した後に返される反論(価格・機能・信頼性など)は、
まず「そういうご懸念があるかと思います/それは良いポイントです」と
受け止めることが重要。その後、提案を再提示する(強み・差別化・改善策を加える)
例:「ご懸念の価格については、確かに初期投資がかかるという点はあります。
ただ、その分アフターサポートを手厚く入れており、導入後~ヶ月でコスト回収が見込める
試算をお出しできます。」数字・具体例を提示して、他社や過去事例との比較をすることで信頼度を上げる。
クロージング時に断られたときの “再浮上” トーク
クロージングフェーズで断られたときも、「終わり」と捉えずに
“再浮上(後からまた検討してもらう/次につなげる)”のトークを用意しておくことが
成果を左右します。例:
「本日はこのお話をじっくり検討していただき、ありがとうございました。
もしよろしければ、今後ご参考になりそうな導入事例やコストシミュレーションの資料を
お送りいたします。ご都合よろしいタイミングでまたお話させてください。」また、「今日決断できなくても、いつ頃ならご判断可能か」を伺うことで、
次のアクションプランを作成する。
現場で応用する方法とトレーニング法
応酬話法を営業現場で実際に定着させ、成果につなげるには、トレーニング体系の整備とナレッジ共有の仕組化が不可欠です。以下にその具体的な方法を示します。
ロールプレイで習得する
1対1での反論対応ロープレの設計方法
このプロセスを通じて、自然な応酬話法の対応練習となります。
録音・録画によるフィードバック
ロールプレイや実際商談を録音または録画し、客観的に見返すことで、
話のテンポ、語調、共感の出し方、間(ま)の取り方などを精査できます。特定のテーマ(例:「話す速度」「質問の頻度」「顧客の反応」)に絞って聞き返すことで、
改善点の絞り込みが容易になります。
反論フレーズごとのパターン練習
代表的な断り文句(予算・比較・タイミングなど)ごとに、応酬形式を整理し、
複数パターンの切り返しを準備しておくと現場で選択しやすくなります。例えば「予算がない」→「Yes but 法」「クッション話法」「PREP 法」など
複数型を準備してロープレで試すことで、状況に応じた使い分けが可能になります。
トークスクリプトへの落とし込み
応酬話法をスクリプトに組み込む方法
標準トークの中に、応酬話法の型(Yes but 法・PREP 法など)を分岐パターンとして
組み込みます。たとえば、反論があった場合に「おっしゃる通りですが…」
「確かに懸念は…しかし…」という流れをスクリプト化します。
汎用トーク vs 個別カスタマイズ
まずは汎用トークをベースに習熟し、その後ペルソナや商談フェーズに応じてカスタマイズするのが現実的なステップです。
CRM・SFAツールと連携した運用
SFA/CRM で反論パターンごとの成功/失敗データを記録し、
どの応酬トークが有効だったかを可視化します。月次レビューで「この言い回しで反応率が上がった」などを共有し、
スクリプトを更新するPDCA サイクルを回すことが可能です。
育成や営業チームでの共有方法
ナレッジ共有の仕組み化(Notion / スプレッドシートなど)
応酬話法の成功事例・NG事例・応答テンプレートなどを Notion や
スプレッドシートに体系的に整理・蓄積。担当フェーズや顧客タイプ別にラベルをつけ、検索しやすく管理しておくことで
チーム全体の知見をシェアできます。
ミーティングでの「反論事例共有」
定例営業会議/朝会で「先週出てきた断りフレーズ」と「その反応でどう対応したか」
を共有する時間を設ける。成功事例には拍手・評価を、うまく対応できなかったケースにはチームで改善策を
話し合う場を作ることで、ナレッジが蓄積され、チーム全体のレスポンス力が
高まります。
マネージャーがフィードバックを入れるコツ
ロールプレイや実商談の録音をもとに、**具体的に「ここは〇〇の言い回しで
もっと共感が伝わった」「ここは少し理屈が飛びすぎていた」**など、
細かく指摘できると効果が高いです。「なぜその言い方にしたのか?」と質問しながら内省を促すスタイルが望ましい。
これによって担当者自身が改善点に気付き、自律的にスキルを上げていけます。
まとめ:営業対話を前進させる技術
本記事では、営業現場で顧客の「断り」や「反論」に直面した際に、信頼関係を損なわずに会話を前進させる「応酬話法」の重要性と実践方法が解説されました。
多くの営業現場では、反論にうまく対応できずに商談が止まってしまうケースが後を絶ちません。こうした課題に対しては、営業個人のトーク力に頼るのではなく、組織全体で「成果につながる会話の型」を構造的に設計・実装することが求められます。
成果が出る“型”を営業組織にインストール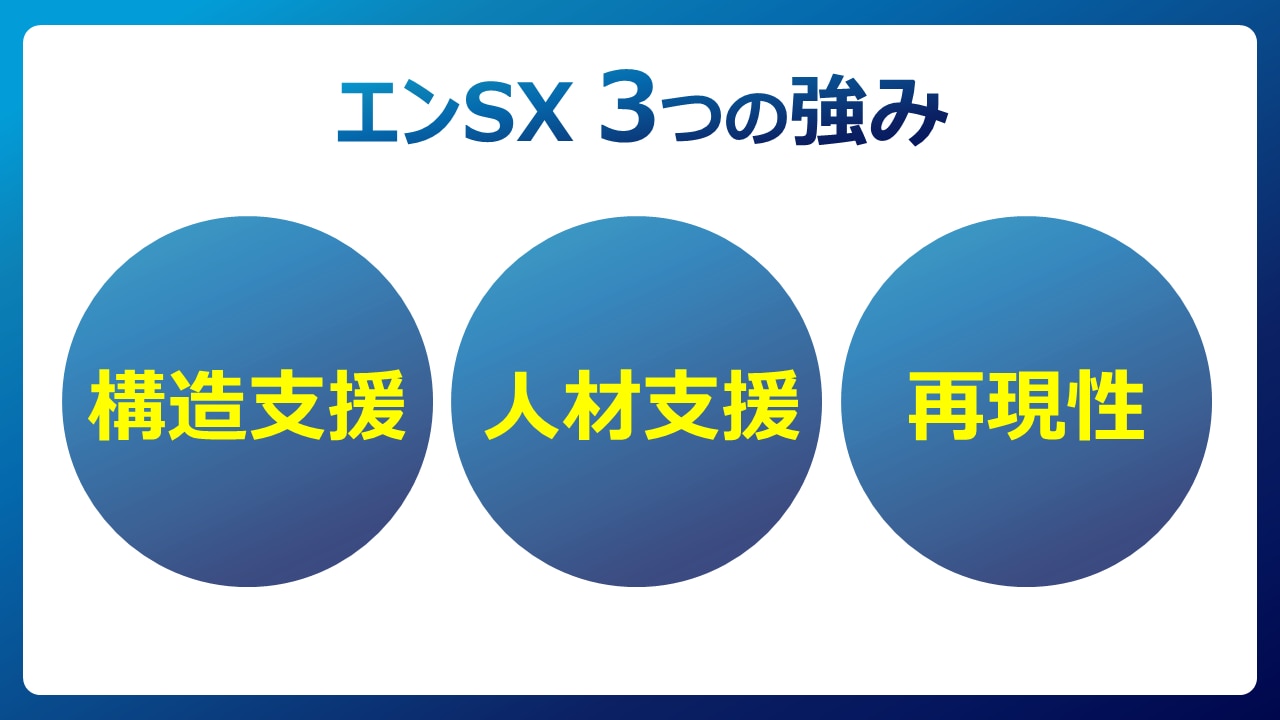
応酬話法のような「反論対応力」も、属人化せず“再現できる型”として組織に仕組み化することが成果のカギ。
エンSXでは、営業現場の構造支援からスクリプト設計、人材育成まで一気通貫でサポート。属人的な営業から脱却し、成果が出るインサイドセールス体制の構築を支援します。
👉 成果が出るインサイドセールスを始めたい方は、まずはこちらの資料をご覧ください。
インサイドセールス支援サービス資料(無料DL)