
SaaSで営業代行を活用するなら?失敗しない選び方と導入戦略を解説
SaaS企業にとって営業活動の立ち上げや拡大は、スピードと再現性が問われる領域です。営業組織を内製するには時間もコストもかかる中、「営業代行を活用できないか?」と考える企業は少なくありません。
しかし、SaaSの営業は一般的な商材と異なり、継続課金モデル特有の営業プロセス、LTV設計、インサイドセールス主導の分業体制が前提です。これを理解せずに営業代行を導入すれば、成果が出ないどころかブランド毀損のリスクもあります。
この記事では、SaaS企業が営業代行を検討する際に必ず押さえるべきポイントを網羅的に解説。代行の正しい活用方法から、成功するための設計、依頼先の選び方まで、「検討段階の不安」に応える内容をお届けします。
目次[非表示]
SaaS営業における「営業代行」とは何か?
SaaS企業にとって「営業代行」は、急成長や人員不足に対応する柔軟な手段として注目されています。ただし、導入の際には誤解や適性、構造的な違いを理解しておく必要があります。
営業代行の基本定義とよくある誤解
営業代行とは、企業が自社の営業活動(リード獲得、アポ取得、商談、契約など)を外部の専門会社に委託することを指します。
「アポ取りだけ」ではない、代行の多様な形態
「営業代行」と聞くと、いわゆる“テレアポ部隊”のイメージを持たれがちですが、実際は以下のように多様化しています。
▼ 営業代行の形態と業務範囲の違い
代行会社によって対応可能な領域は異なるため、自社の体制や目的に合わせて選定する必要があります。
受注まで請け負う代行と、商談設定までの代行の違い
営業代行の導入時には、どこまでを任せるかを明確にすることが極めて重要です。
商談設定型は、自社営業にバトンを渡す前提での支援。
受注型は、商談から契約までを代行が担います。
どちらが適しているかは、自社の営業スキル・商材難易度・顧客との関係性構築の重要性によって異なります。
SaaSにおける営業の特徴と代行との相性
SaaSは「売って終わり」のビジネスではなく、継続課金モデルです。そのため、営業代行のあり方にもSaaS特有の配慮が求められます。
インサイドセールス主導の分業体制
多くのSaaS企業では、以下のような分業体制が構築されています。
▼ SaaS営業の典型的な分業構造
代行が担えるのはSDR/BDR領域が中心。ここを強化することで、自社のIS・FSのリソースを提案・契約に集中させられます。
LTV・CAC・解約率が影響する営業構造
SaaSでは、1件の受注が短期的に黒字になるとは限りません。むしろ継続率や回収効率が営業投資の妥当性を判断する軸となります。
▼ SaaS営業で重要な3指標
営業代行を使うことでCACが上がりすぎる場合、LTVが十分高くなければ費用対効果が合いません。
単純な売り切りモデルとの違い
SaaS営業は、販売そのものよりも“継続利用”が収益を左右するため、営業代行の評価指標も変わります。
短期契約や無理な押し込みは、後の解約リスクを高めるため、SaaSでは中長期視点の代行パートナー選びが必須です。
SaaS企業が営業代行を検討する背景とタイミング
SaaS企業が自社営業だけでなく、営業代行を検討するのには一定のタイミングや課題が重なることが多いです。以下は典型的なフェーズと、よくある課題/ニーズです。
営業代行を検討する3つの典型フェーズ
SaaS企業で「営業代行を使おうか」と考え始めるフェーズは、大まかに以下の3つが典型です。
① 営業立ち上げフェーズ(初期スタートアップ)
このフェーズでは、営業体制がまだ整っていなかったり、人員・ノウハウが不足していたりします。代行を使うことで、「早く市場に接触を持たせる」「初期の顧客反応を得て仮説を検証する」ことが可能になります。
主な特徴:
営業担当者の経験が浅く、トークやプロセスが未確立
リードの流入が限定的でフィードバックの量が少ない
スケールモデルを確立する前なので固定費を抑えつつ成果を見たい
この段階で営業代行を入れることによって、最初の数週間〜数ヶ月でアポ取得数を確保し、自社商材のフィット感/ペルソナ仮説を高速に修正できるようになります。
② 営業改善フェーズ(商談率・受注率の壁)
営業はある程度回ってきたけれど、商談→成約への転換率が伸び悩む、商談数が増えてきたが追い切れていない、営業の時間の使い方に無駄がある、といった壁に直面するフェーズです。
参考数値として、SaaS企業の商談化率(有効リードから商談まで持っていく割合)は、**3.5%〜20〜30%**といった幅が業界で見られます。
また、受注率(商談→契約)の目安が約 20%前後というデータもあります。
このフェーズで代行を使う動機:
営業トーク/商談設計の改善が急務
提案資料や比較表など営業支援コンテンツの弱さが露出する
インサイドセールス/商談フォローの工数が圧迫されはじめて、自社だけでは処理しきれなくなる
代行を部分的に入れることで、「商談率改善」や「営業担当のブラッシュアップ」「フォロー体制の補強」が期待できます。
③ 営業拡大フェーズ(再現性のある型を増幅)
営業プロセスが確立し、ある程度の成果が見えてきた企業は次に「規模を拡大する」フェーズに入ります。
この段階での特徴:
商談・受注までの営業サイクルが再現可能になっている
ペルソナ/ターゲット市場が明確で、ある程度営業リソースをスケールできる基盤ができている
内製チームを増やす、地域や業界を広げる、チャネルを増やすなど拡張のフェーズ
この時期に営業代行を使う意義は、「拡大速度を上げる」「営業コストを可変化する」「マーケティングや商品開発との協業を加速させる」ことです。
SaaS企業のよくある課題とニーズ
営業代行を検討する背景には、上記フェーズそれぞれで共通・個別の課題があります。以下、頻出するものをまとめます。
内製化するには時間とリソースが足りない
営業人材の採用・育成には通常数ヶ月から半年以上を要することが多く、
特にスタートアップではそれがボトルネックとなる。トークスクリプト・競合比較表などのコンテンツ作成、営業プロセス設計など、
営業の土台構築には業務工数とナレッジが必要。代行を使うことで、これらを一時的に補いつつ、自社でノウハウを蓄積できるようにする。
インバウンドから商談化率が低い
ウェブサイトへの訪問や資料請求などマーケティング活動はうまく機能しているが、
それが商談まで繋がらないケース。
例えば、インサイドセールスでの商談化率が 3.5%~20~30%といったレンジであること。
原因として、リードの質のばらつき、対応遅れ、トーク力不足、顧客のニーズ把握不足などがある。
このニーズを抱えた企業が代行を使うことで、商談化率を短期間で改善することを目的とする。
商談化率改善を外注で実現するには?
「インサイドセールスの商談化率が伸び悩む」 そんな課題を感じているSaaS企業にとって、外部の力をどう取り入れるかは重要な検討ポイントです。
とはいえ、外注にはメリットとリスクが共存するため、「何を・どこまで任せるか」を見極める必要があります。
その検討に役立つ、実践的な資料をご用意しています。
受注まで一気通貫の営業を社内で担えない
商談設定はできても、提案→交渉→クロージングまで持っていく人材が不足、
あるいはその経験・実績が不足している。
特に複雑な SaaS 商材(機能が多い、カスタマイズが必要、複数ステークホルダーを
巻き込むタイプ)ではこの傾向が強い。また、カスタマーサクセスや導入後のフォローと営業の橋渡しが弱いため、
「契約後に離脱する」「追加販売ができない」などの問題が発生しやすい。営業代行を「受注まで請け負う型」として使うことで、この通貫性を補うケースがある。
ただし、その代行会社に SaaS 商材理解・クローズ力・フォロー体制が
あるかどうかが重要な選定基準になる。
SaaS営業代行の主なタイプと選び方
SaaS企業にとって、営業代行は単なるアウトソーシングではなく、「成果を上げるための戦略パートナー」となり得ます。しかし、代行の形態には複数あり、目的やフェーズに応じて適切な選定が不可欠です。
営業代行の分類とそれぞれの役割
営業代行にはいくつかのパターンがあり、それぞれ担う業務範囲や得意とするフェーズが異なります。以下に代表的なタイプを整理します。
▼ 主な営業代行タイプと役割
これらの型を組み合わせてハイブリッドで依頼することもあります。重要なのは、自社の営業フローのどこがボトルネックかを明確にすることです。
インサイドセールス代行(リード対応〜商談化)
主にWeb問い合わせや資料請求リード(MQL)への対応を行い、SQL(商談化)への転換を担います。
商談数の安定確保やIS体制立ち上げ初期に効果的。
スピードと量が求められるため、SaaSに特化した対応スクリプトや業界知識がある代行会社が望ましい。
テレアポ型アウトバウンド代行(SDR型)
コールドリードやリスト先への架電・DM送付・接触打診を行うスタイル。
SDR(Sales Development Representative)に近い役割で、新規開拓を狙う際に活用されます。
リスト作成からスクリプト作成、初回接触までを請け負うため、スクリプトの柔軟さと分析力が重要。
フィールドセールス代行(クロージング型)
インサイドセールスが創出した商談に対して、提案〜条件交渉〜クロージングまで対応。
SaaSの特性(継続課金・カスタマイズ・契約形態)への理解が必須で、汎用的な営業スキルでは不十分。
BtoB SaaS経験者による提案力がある代行会社を選ぶことが成否を分けます。
選定時に見るべきポイント
SaaS営業において営業代行を活用する際、パートナー選びの失敗は商談の質低下やLTV損失に直結します。以下の観点を必ず確認しましょう。
SaaS営業の実績・業界理解の有無
「業界特化」「SaaS商材に強い」と明記していても、具体的な実績があるかは別問題。
特に以下を確認:
同業または類似業界の支援経験
顧客単価・営業プロセスの類似性
商材理解にかかるリードタイムと研修体制
BtoB SaaSは検討期間が長く、複雑な意思決定構造があるため、ITリテラシーの高い代行チームが必須です。
KPI設計とフィードバック体制の柔軟性
アポ数だけを追うと質の低い商談が増えるリスクあり。代行会社とKPI設定を共創できるかが重要。
例:
「商談化率」や「有効リード数」での評価
定例MTGでのスクリプト改善・案件レビュー
フィードバックに対する改善スピード
KPIが「成果連動型」である場合も、短期数字に偏らない設計がポイントです。
自社の営業プロセスとの親和性
自社の営業フェーズ(インサイド→フィールド→カスタマーサクセス)との連携がスムーズにできる体制であるか。
CRM(SalesforceやHubSpotなど)への入力・連携をどう行うかの運用設計も重要。
担当者が変わらない体制(固定チーム制)をとっているかもチェックポイントです。
SaaS営業代行を成功させるための前提条件
営業代行を導入して成果を上げるには、単に代行先に任せるだけでなく、社内での準備や体制づくりが不可欠です。ここでは、成功のための前提条件を具体的に解説します。
「丸投げしない」ための社内準備
代行先に丸投げすると、コミュニケーションロスや認識齟齬が起きやすく、成果が出づらくなります。まずは以下の3点を整備することが重要です。
理想の顧客像(ICP)の明確化
ICP(Ideal Customer Profile)は、代行先が狙うべきターゲット像を指し、商談成功率を左右します。
業種・従業員数・利用環境・導入目的など、具体的に設計し共有しましょう。
スクリプト・ナレッジの事前共有
商談で使うトークスクリプト、よくある反論対応、製品の特徴や競合情報は代行先に事前にしっかり共有。
これにより、現場でのズレや混乱を防ぎます。
営業代行先との伴走体制の構築
定例ミーティングやチャットでの連絡体制を設け、双方で進捗や課題をこまめに共有。
KPIの振り返りやスクリプト改善も伴走型で行うことが成功の秘訣です。
よくある失敗パターンと対策
営業代行で失敗する企業に共通する課題を整理し、それぞれの対策を提案します。
:
▼ 失敗パターンと対策一覧表
KPIが合っていない(量だけ・質だけを追う)
例えば「アポイント数」のみを追うと、質の低いアポが増えて商談が続かないケースが多発。
逆に「受注率」だけを重視しすぎると、新規リード獲得数が減少するリスクがあります。
両者をバランスよく設計し、数値のトレードオフを理解したKPI設定が必須。
商品理解が浅いままトーク開始
SaaSは競合も多く差別化が難しいため、代行担当者にしっかりとした商品教育を行わないと、効果的な商談ができません。
定期的な勉強会やQ&Aセッションを設けて商品知識をブラッシュアップする必要があります。
社内との連携不足でリードが放置される
商談化したリードが社内に適切に引き継がれず、そのまま放置されるケースが散見されます。
CRMやSFAとの連携、リードステータス管理のルール策定、社内担当者との明確な役割分担が不可欠。
インサイドセールス支援との違いと併用戦略
SaaS営業で成果を最大化するためには、営業代行だけでなく、インサイドセールス(IS)支援との使い分け・併用が重要です。ここでは両者の違いを明確にし、効果的な段階的活用方法を解説します。
営業代行とインサイドセールス支援の違い
営業代行とインサイドセールス支援は一見似ていますが、役割や運用形態に大きな違いがあります。
▼ 営業代行とインサイドセールス支援の比較表
運用主導権の違い(委託型 vs 伴走型)
営業代行は**「丸ごと外注」**の性質が強く、日々の運用や指示系統は代行先に委ねられます。
インサイドセールス支援は、自社が主体的に運用を習得するための**「教育・伴走」**が主軸。
これにより、自社の営業組織成長を促しながら、徐々に内製化を目指します。
チーム構築への影響
営業代行の場合、代行会社が専任チームを用意し迅速に立ち上げ可能ですが、社内にノウハウは蓄積されにくいです。
IS支援は、専任トレーナーやコンサルタントが自社メンバーを育成し、将来的な自走力向上を目指します。
業務の標準化・再現性に与える効果
代行は代行会社の成功パターンをそのまま持ち込みやすく、標準化は早いものの自社独自性は薄れがち。
IS支援は自社特性を踏まえた業務フロー設計に注力し、長期的な再現性向上に寄与します。
併用・段階的活用によるスケーラブルな営業戦略
両者を組み合わせた段階的活用で、より効率的に営業体制をスケールさせる戦略が推奨されます。
初期は代行で回し、のちに内製化
新規市場開拓や営業立ち上げフェーズでは、代行を使って短期間で成果を出しつつ、営業の基本を固めるのが有効。
その後、ノウハウが溜まった段階でIS支援を受けながら内製チームを構築・拡大していきます。
スクリプトやデータを支援会社と共同設計
代行もIS支援も、スクリプトや顧客データ、商談履歴の分析は欠かせません。
これらを代行会社や支援会社と協働で改善・最適化し続けることで、精度の高い営業活動が可能になります。
成果が出た領域から社内に移管する方法
まずは成果が出やすい、または標準化しやすい領域(例:リードナーチャリングや初回アポ取得)から社内化。
クロージングや高度提案は代行に残すなど、段階的に移行しながらリスクを分散します。
まとめ:営業代行の活用法を見極める
SaaS営業における営業代行は、営業体制の柔軟な強化策として有効ですが、目的やフェーズに応じた適切な選定と運用が不可欠です。
多くの企業が「成果が出ない」「代行任せで内製化できない」といった課題に直面します。
こうした課題を乗り越えるには、単なる外注ではなく、“構造設計”の視点で営業体制を見直し、成果につながる仕組みづくりを進めることが重要です。
成果が出る“型”を営業組織にインストール
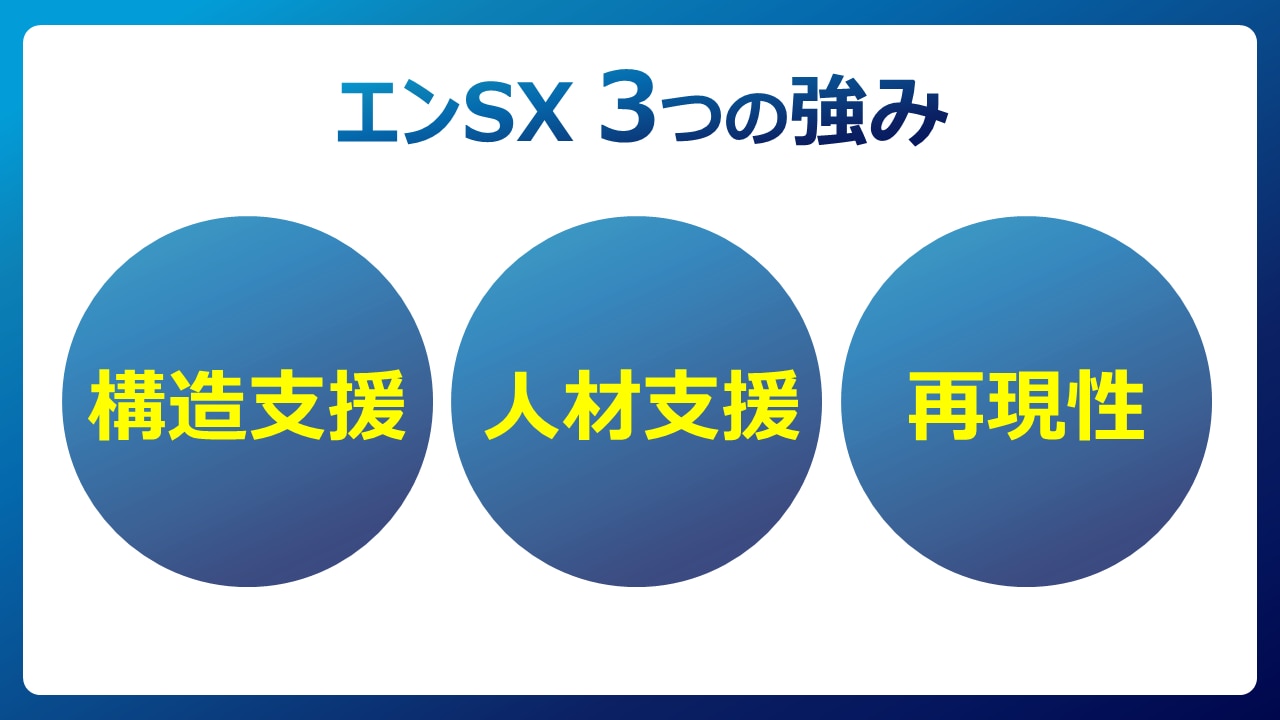
SaaS営業の分業体制やLTV・CACなど複雑な構造に対応するには、仕組み化された営業プロセスが不可欠です。
エンSXでは、構造支援×人材支援×再現性のある運用によって、代行・内製どちらの形でも成果を支える設計をご支援しています。
👉 成果が出るインサイドセールスを始めたい方は、まずはこちらの資料をご覧ください。
インサイドセールス支援サービス資料(無料DL)













