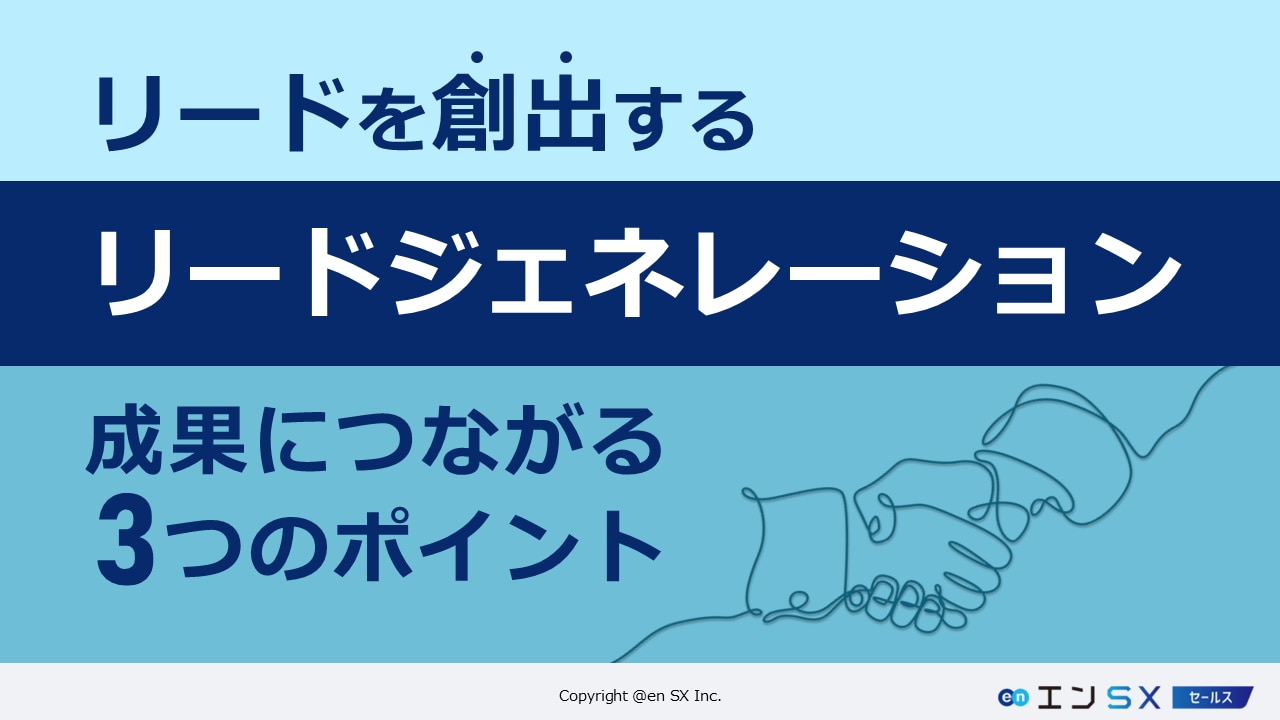BtoBで成果を上げるデマンドジェネレーション完全ガイド
BtoB企業の営業・マーケティング担当者にとって、「デマンドジェネレーション」は売上拡大の鍵となる重要施策です。しかし、多くの企業がリード獲得に留まり、実際の商談や受注に結びつけられずに悩んでいます。
本記事では、単なるリードジェネレーションとの違いを踏まえ、マーケティングからインサイドセールス、営業へと続く「成果を生む仕組み」の全体像を深掘り。具体的なプロセスやKPI設計、部門間連携のポイントをわかりやすく解説します。自社の営業成果を本質的に改善したい方に役立つ内容です。
目次[非表示]
デマンドジェネレーションとは?BtoBでの本質的な意味
デマンドジェネレーション(Demand Generation)とは、潜在顧客が製品やサービスへのニーズを認識し、購買意欲を持つまでの一連のマーケティング活動を指します。特にBtoBでは、リードの獲得にとどまらず、顧客の認知・理解・信頼を段階的に育て、商談・受注へと導くプロセス全体が重要です。
リードジェネレーションとの違いと役割分担
リードジェネレーションの定義と特徴
リードジェネレーションは、見込み顧客(リード)を獲得する活動を指します。代表的な施策には、資料ダウンロード、セミナー参加、問い合わせなどがあります。
特徴:
顕在層へのアプローチが中心
数値化しやすく、短期的な効果を測定しやすい
主に「リスト獲得」を目的とする
📊 日本企業の実態
資料請求サイトから得られたリードの商談化率は 約7〜8% にとどまっているの現状です。
デマンドジェネレーションの範囲と目的
デマンドジェネレーションは、認知〜ナーチャリング〜商談化までの全プロセスを対象とし、特に潜在層の顧客との関係構築が主目的です。
主な目的:
潜在層への教育・認知向上
ブランドへの信頼醸成
リードの質と商談化率の向上
📌 例
「展示会参加者へのホワイトペーパー送付」「ウェビナー参加者へのフォローアップ」「メールナーチャリングによるスコアリング」などが該当します。
両者の関係性とBtoB営業への影響
なぜBtoBで重要視されるのか?営業成果との関連性
BtoB営業の特性と購買プロセスの複雑さ
BtoBの購買プロセスは、複数の部門・担当者が関与し、平均で3ヶ月〜6ヶ月以上かかることが一般的です(出典:ベネクロ株式会社)。
特徴:
複数意思決定者の合意が必要
高単価・中長期検討型が多い
問題認識 → 情報収集 → 比較検討 → 社内承認 と段階が多い
📊 参考:日本企業のBtoB購買活動
「営業に初めて連絡を取るのは、購買プロセスの70%以上が完了した後」という傾向があります。
リードから商談化・受注までの課題
日本企業のマーケティング・営業現場では以下の課題が顕在化しています。
💬 現場の声
「せっかくリードを獲得しても、質がバラバラでフォローしても全然商談にならない」
デマンドジェネレーションが解決するポイント
デマンドジェネレーションの導入により、以下の課題に対処可能です。
📊 成果事例:
日本のBtoB企業における調査では、初回接触が2日以内かつ2〜3回の接触で商談化した企業群の商談化率は50%以上に達しています。
デマンドジェネレーションの全体プロセスとKPI設計
認知から商談化までのフェーズ解説
デマンドジェネレーションでは、顧客が「自分の問題を認識する」段階から「商談・受注に至る」段階までを複数フェーズに分け、それぞれで適切な施策とKPIを設けることが重要です。一般的には次のようなフェーズを想定します。
認知・興味喚起フェーズ
リード獲得フェーズ
リードナーチャリング(育成)フェーズ
商談化・クロージングフェーズ
以下、それぞれのフェーズの役割と具体的なポイントを見ていきます。
認知・興味喚起フェーズの役割
認知・興味喚起フェーズは、潜在顧客(まだ明確なニーズを自覚していない層)に対して、自社の存在や業界の課題・解決策のヒントを提供し、「この会社・この製品を知っておこう」と思ってもらう段階です。
このフェーズで重視すべきことは:
認知を広げるコンテンツ(ブログ、記事、レポート、業界動向など)の発信
SEO や広告で対象ターゲットがアクセスしやすい導線をつくる
ソーシャルメディアや業界メディアでの露出を図る
ブランドや専門性を感じさせる情報提供による信頼の種まき
この段階では、数よりも質の高い関心を引き出すことがポイントです。
リード獲得フェーズの具体的施策
認知の次は見込み客として登録可能な行動を促すフェーズです。具体的な施策としては次のようなものがあります:
ホワイトペーパー・業界調査レポートなど、ダウンロード可能な資料提供
ウェビナー・オンラインイベントの開催・参加受付
無料トライアルやデモ申込フォーム設置
有料広告(リスティング広告、SNS広告等)で特定ターゲットにアプローチ
LP(ランディングページ)の最適化(フォームの簡潔化・誘導動線の明確化)
これらの施策により、「見込み客(リード)」を獲得します。
リードジェネレーション施策を体系的に学ぶには?
リード獲得の重要性は理解していても、「具体的にどんな施策をすればよいのか?」「成果に結びつけるための型はあるのか?」といった実践面で悩む声は少なくありません。
そんな方のために、リードジェネレーションに特化した資料をご紹介します。ホワイトペーパーやセミナーだけでなく、効果的なアプローチ方法を知りたい方にとって、ヒントが詰まった内容となっています。
リードナーチャリングフェーズの重要性
リードナーチャリングフェーズは、「獲得したリード」を育てて商談に繋げるフェーズです。この段階が弱いと、リードを大量に獲得しても、商談化しない・放置される割合が高くなってしまいます。
主な要点は:
メール配信、ステップメール、ニュースレターなどを通じて定期的に接点を持つこと
リード行動(資料ダウンロード、ウェブサイト訪問、イベント参加など)を
トラッキングし、スコア付けすること(スコアリング)セグメンテーション(業種、役職、興味内容など)に応じたパーソナライズされた
内容を提供すること見込み度が上がったタイミングで営業やインサイドセールスに引き渡すルールを
明確にすること
日本国内でも、電通B2Bイニシアティブなどが「スコアリング+ナーチャリング施策」によって、リード育成の効果を高めることを推奨しています。
商談化・クロージングフェーズのポイント
最後は商談・受注に至るフェーズです。ここでは次の点が重要になります:
リードが SQL(営業対応可能な見込み客)として認定される明確な基準を設定すること
営業側でのデモ・見積もり・提案書などの準備を迅速かつ的確に行うこと
見込み客の疑問や障壁(コスト、技術、サポート体制など)を解消するための情報や資料を用意すること
営業とマーケティング/インサイドセールス間で連携を取り、進捗状況・障害情報を共有すること
商談化率・成約率を上げるには、「質の良いリード」「スムーズな引き渡し」「営業の提案力」が鍵となります。
各フェーズの代表的KPIとその計測方法
各プロセスフェーズごとに主要なKPI(指標)を設定し、定期的に測定・改善することで、デマンドジェネレーションの効果が見えるようになります。
認知段階の指標(例:Webトラフィック、コンテンツ閲覧数)
リード獲得段階の指標(例:リード数、資料ダウンロード数)
ナーチャリング段階の指標(例:メール開封率、反応率)
商談化段階の指標(例:商談化率、成約率)
MA・CRM・SFAを活用したデータ管理のポイント
各ツールの役割を明確にし、それらの連携をスムーズにすることで、KPI測定とプロセス管理の精度が上がります。
MA(マーケティングオートメーション)の役割と活用法
メール配信の自動化、スコアリング、リードのセグメンテーションが可能です。
行動トリガー(例:資料ダウンロード後のメール送付、ウェビナー参加後のフォローアップ)を
設定することで、見込み度の上昇を検知・対応できます。過去データに基づく開封率・クリック率等の分析で、メール文面や配信タイミングを継続的に
最適化できます。
CRMでのリード・顧客管理の基本
リードの属性情報(業種、企業規模、役職など)および行動履歴を一元管理します。
リードフェーズ(例:認知 → MQL → SQL → 商談中 → 受注)の定義を明確化し、
各フェーズの基準と責任者を決めておきます。顧客との接触履歴・商談内容・見積履歴などを記録し、営業判断の材料として
共有できるようにします。
SFAで営業活動の見える化と連携強化
営業部の活動(アポイント取得数、提案数、フォローアップ状況など)を定量的に把握できます。
リードを営業へ引き渡す際のタイムラグや引き渡し後の対応状況も追えるようにすることで、
ムダ・ボトルネックを早期に発見できます。営業側ダッシュボードを用いて、どのリードがどのナーチャリングフェーズからきているかを可視化し、
マーケティング施策の影響を理解できるようにします。
ツール間のデータ連携の注意点
データの重複・不整合を防ぐこと:たとえば、複数のフォームやツールで
同じ企業・人物が登録されていたら重複を統合する。スコアリング基準・リードフェーズの定義をマーケティング・営業間で共有し、
ツールで共通のルールを使う。更新頻度・タイムラグに注意する:たとえば MA → CRM への情報反映が
遅いと判断が誤る可能性がある。プライバシー・個人情報保護関連法令(個人情報保護法、EUの GDPR 等)の順守と、
内部でのデータ利用ルールの明文化。
マーケティングとインサイドセールスの連携設計
マーケティング部門とインサイドセールス(Inside Sales)が密に連携することで、リードの商談化・受注率を高められます。そのための設計ポイントを整理します。
部門間での情報共有とSLA(サービスレベルアグリーメント)
SLA設定の目的と内容例
目的:
マーケティングとインサイドセールスの役割と責任を明確にし、期待値を共有することです。
リード引き渡し後の反応遅延や見込み度の低いリードが営業を圧迫する事態を防ぐことです。
両部門の協業を通じて、営業パイプライン(商談候補)の質と量を安定させることです。
内容例:
日本のマーケトランクなどのコラムにも、こうした SLA を設定することで「セールスとマーケティングの間に起きがちな誤解や責任のモレ」が減り、効率的になるという事例が紹介されています。
リードの受け渡し基準と品質管理
受け渡し基準の設定:属性・行動によるスコアリングを使って、
最低限の要件を満たしたリードのみを“営業対応可”として引き渡します
(例:役職が管理職以上・予算規模が一定以上・ウェビナー参加経験あり 等)。品質管理:営業側が「このリードは商談化できなかった」ケースの調査とフィードバックを受け、
マーケティング側でリードの質を改善するループを回します。拒否理由の記録:営業が受け渡したリードを拒否する理由を記録(例:役職不適合・興味不足・予算なしなど)し、
受け渡し基準やマーケティング施策を改善します。
定期的なコミュニケーションと改善活動
定例ミーティング(週次/月次/四半期)を設け、KPI の進捗・リード引き渡し状況・商談化率などを
双方で確認します。問題が見られた部門が何かを発見し、その原因を共有、対策を講じる。
たとえば、引き渡したリードの商談化率が低い → リード品質の基準を見直す、
ナーチャリングプロセスを強化する。SLA の見直しを定期的に行う:マーケット環境や内部体制が変われば、基準や目標も更新が必要です。
日本の事例でも「半年に1度 SLA や KPI の見直しを実施している」企業が成果を出しているケースがあります。
インサイドセールスの役割と期待される成果
インサイドセールスのミッションと役割範囲
マーケティングから渡されたリード(MQL)を受け取り、育成を含めて商談可能(SQL)な状態にまで
引き上げることが主なミッションです。また、新規ターゲットに対するアウトバウンド活動を担当する場合もあります(BDR 型)。
一方で、反響型(SDR 型)ではマーケティング主導のインバウンドリード対応が中心になります。フィールドセールス/営業チームとの情報共有や顧客の声収集も重要な役割です。
どのような課題を持っているか、どのコンテンツが響いたか等をフィードバックします。
リードの育成から商談創出までのフロー
マーケティングが創出した MQL をインサイドセールスに引き渡す
インサイドセールスが初期接触(電話/メール等)を行い、リードの状況・ニーズをヒアリングする
関心度・購買準備度に応じてリードを育成(ナーチャリング):追加資料提供・ケーススタディ紹介・ウェビナー案内等
リードが一定基準(SQL)を満たしたと判断されたら、フィールドセールス/営業部門に商談として引き渡す
このフローを明文化し、担当者とタイムラインを共有することが成果を出す上で欠かせません。
成果指標と評価方法
主な指標とその評価方法は次の通りです。
具体的な連携フロー例(例:リードナーチャリングから商談化まで)
マーケティングからインサイドセールスへのリード移行
マーケティング部門は、リードスコアリング基準(属性スコア + 行動スコア)を用いて
「一定以上のスコアを超えたリード」を MQL と認定します。MQL の受け渡しは、SLA によって「毎営業日または翌営業日の朝まで」に行うなど、
時間軸の基準も設けます。
インサイドセールスのフォローアップ手法
初回接触は電話またはメールで、リードの関心や課題をヒアリングする。
適切なフォローアップのスクリプト(質問項目・ケーススタディ紹介など)を用意し、見込み度を測る。
ウェビナー案内、追加資料提供等でナーチャリングを行い、
SQL 判定のトリガー(例:見積依頼・商談希望など)があれば速やかに対応する。
営業への商談引き渡しのタイミングと基準
商談引き渡し基準を明文化:
例として「予算が見込める」「意思決定者が関与している」「導入スケジュールが6か月以内」など。インサイドセールスが SQL と判断した時、営業へ引き渡す。
引き渡し時にはこれまでのヒアリング内容・関心を持ったコンテンツ・対応履歴などを付帯情報として渡す。引き渡し後の営業フォローアップ時間にも SLA を設け、
たとえば「営業は引き渡された商談を 48 時間以内に着手する」などが望ましい。
成果を出すデマンドジェネレーションの運用体制と実践ポイント
属人化を防ぐためのスクリプトとプロセス設計
トークスクリプトの標準化と活用方法
営業やインサイドセールスの会話内容を標準化することで、担当者ごとの差を減らせます。特に「課題の特定」「予算の有無」「導入時期」などの基本質問をあらかじめスクリプト化しておくと、商談の質が安定します。定期的な見直しで、成果が出やすい言い回しなどを更新していくことも大切です。
業務フローの明文化と共有
リードの獲得から商談、成約までの流れをフローチャートにし、関係者全員が共通理解を持つことが重要です。どのタイミングでどの部門が対応するか、どの情報を引き継ぐかを明確にすることで、業務の抜け漏れを防ぎます。
教育・トレーニング体制の構築
属人化を防ぐには、定期的な教育体制の構築が不可欠です。スクリプトの活用方法やツールの使い方を新入社員や異動者向けに研修し、ロールプレイやOJTで実践力を高めます。また、成功事例や失敗事例をチームで共有する機会を設けると、組織全体のスキルが向上します。
コンテンツマーケティング・ウェビナーなど効果的な施策例
BtoBに適したコンテンツの種類と役割
BtoBでは、意思決定に関わる人が複数いるため、信頼性の高いコンテンツが必要です。たとえば、導入事例やホワイトペーパーは信頼感を高め、課題解決型のコラムは潜在ニーズを引き出す役割を果たします。
ウェビナーの企画・運営のポイント
ウェビナーは少人数でも始められる効果的な施策です。テーマ設定はターゲットの関心事に合わせ、申し込みページやメールでのリマインドも工夫すると参加率が高まります。開催後のアンケートやフォローアップメールで、商談化につなげる流れを整えましょう。
デジタル広告やリターゲティング活用法
広告での集客には、検索連動型広告やSNS広告が有効です。特にリターゲティング広告を活用することで、サイト訪問者に再接触し、コンバージョン率を高められます。広告ごとの成果(クリック率・CV率)を見て、継続的に改善しましょう。
PDCAサイクルの回し方と改善ポイント
データ収集と分析の重要性
施策ごとの成果を把握するには、正確なデータ収集が欠かせません。MAやCRM、SFAなどを活用し、「どの施策がどれだけ商談や受注につながったか」を可視化することで、次のアクションを明確にできます。
仮説検証と施策改善の実践
たとえば「メールの開封率が低い」「ウェビナーの参加率が悪い」といった課題に対し、件名の変更やリマインド回数の調整など、仮説を立ててテストし、数値を見ながら改善を続けることが重要です。
関係部門との連携による継続的改善
マーケティング、インサイドセールス、営業の各部門で定期的にミーティングを行い、成果や課題を共有します。部門間の情報共有がうまくいくことで、プロセスの抜け漏れが減り、成果につながりやすくなります。
成功事例に学ぶデマンドジェネレーションの実践
BtoB企業A社のケーススタディ
課題背景と導入目的
A社はITサービスを提供する中堅企業で、従来はテレアポ中心の営業活動を行っていました。しかし、リードの質が低く、商談化率が10%未満と低迷していたため、マーケティング主導のデマンドジェネレーション導入を決断しました。目的は、質の高い見込み顧客の継続的な獲得と営業活動の効率化です。
具体的施策と運用体制
A社は以下のような施策を段階的に実施しました。
オウンドメディアを活用したホワイトペーパー配布
MAツールによるリードスコアリングの自動化
インサイドセールス部門の新設
月2回のウェビナー開催によるリード獲得と教育
これらの活動を、マーケティング・インサイドセールス・営業の3部門が連携しながら運用しました。
得られた成果と効果指標
導入から半年で以下の成果が確認されました。
インサイドセールスとマーケの連携で成果を上げたポイント
情報共有の工夫とコミュニケーション方法
マーケティングとインサイドセールスは、週1回の定例会とSlackでのリアルタイム連携を徹底しました。リードの反応や問い合わせ内容を即時に共有することで、機会損失を減らすことができました。
部門間SLAの運用実態
SLAでは、MQL(マーケティングが渡すリード)に対して、インサイドセールスが24時間以内に初回アプローチを実施するルールを設定しました。また、対応結果をCRMで記録・分析し、マーケ側がコンテンツやLP改善に活かしました。
ツール活用の成功要因
MA(HubSpot)とCRM(Salesforce)を連携し、スコアに応じてリードを自動振り分け。SFAも併用し、営業までの活動履歴を可視化しました。ツール連携による一元管理が、部門間のスムーズな連携を支えました。
よくある課題とその解決策
リードの質と量のバランス調整
初期段階では数を追うあまり、質が伴わないリードが多く発生しました。そこで、ホワイトペーパーの内容をよりターゲットに絞り込み、CTA(行動喚起)も「サービス紹介」ではなく「課題解決」にフォーカスしました。その結果、スコアの高いリード割合が増加しました。
部門間連携の摩擦解消
当初は「マーケはリードを増やすだけ」「営業は対応しきれない」という不満がありました。これに対して、共通KPI(例:商談化率)を設定し、同じゴールを目指す意識づけを行ったことで、連携がスムーズになりました。
リードナーチャリングの効率化
メールやウェビナーだけでは接触頻度が足りないと判断し、スコアに応じたパーソナライズドメールや、インサイドセールスからの定期フォローコールを加えました。これにより、温度感の高いリードをタイミングよく商談化できるようになりました。
まとめ:商談につながる仕組みづくり
本記事では、BtoB領域における「デマンドジェネレーション」の全体像と、各フェーズごとの設計・KPIについて解説しました。 単なるリード獲得に終始するのではなく、潜在層から信頼を育み、営業と連携して商談・受注に導くプロセス設計が重要です。
一方で、「商談につながらないリードばかり増えてしまう」といった課題に悩む企業は少なくありません。こうした課題を乗り越えるには、成果につながる営業・マーケ連携の“構造”をあらかじめ設計することが不可欠です。
商談化率を高める営業設計を支援
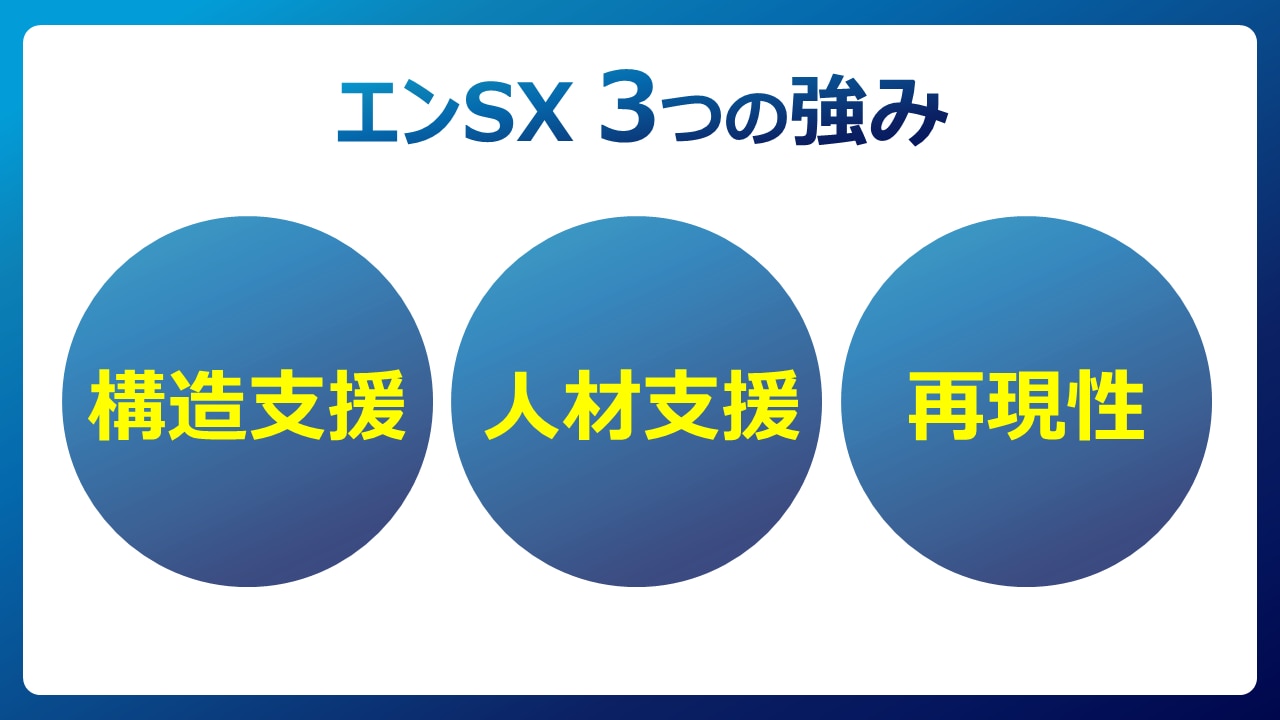
「リードは取れているのに、受注につながらない…」という状況から脱却するには、
成果につながる“営業・マーケの型”を組織にインストールすることが重要です。
エンSXでは、構造設計×人材支援×再現性の仕組みを通じて、インサイドセールスの立ち上げから内製化・KPI改善まで一気通貫で支援します。
👉 成果が出るインサイドセールスを始めたい方は、まずはこちらの資料をご覧ください。
インサイドセールス支援サービス資料(無料DL)